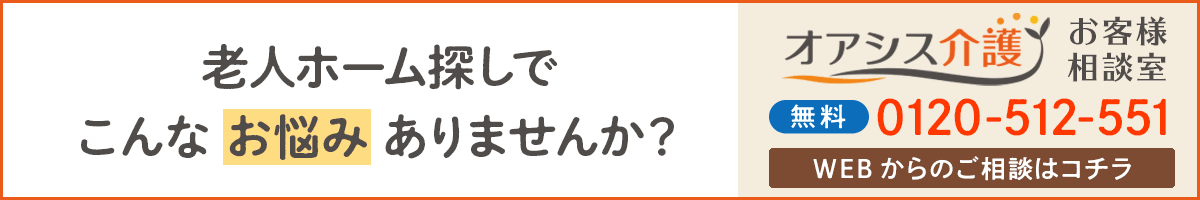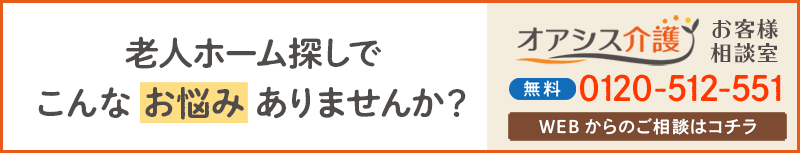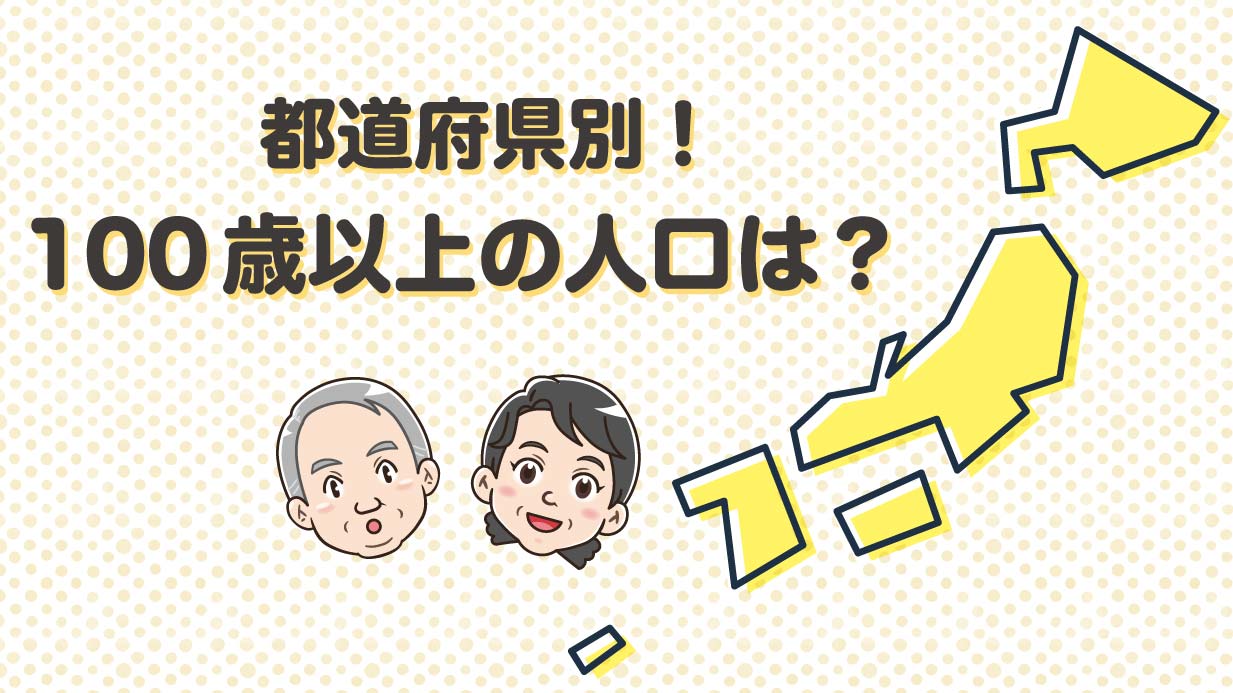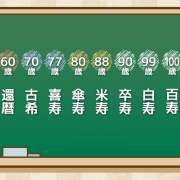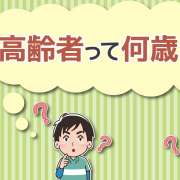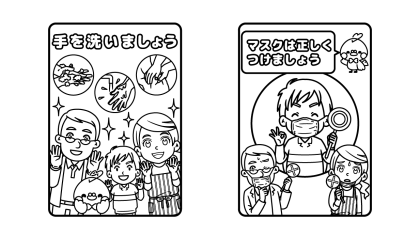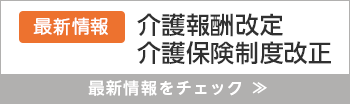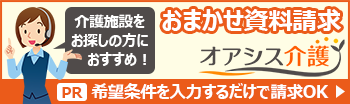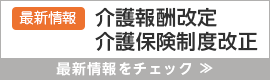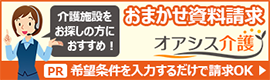*2025年の最新データに更新しました。
ご長寿大国の日本では長生きする方が年々増えていますが、100歳以上の方は現在どのくらいいるのでしょうか。
最新の100歳以上の人口や都道府県ランキング、男女比、推移などをまとめて紹介しましょう。
長生きと性格・血液型の関連性を調査したおもしろいデータも紹介します。
日本には100歳以上のご長寿がたくさんいるっポ。
・2025年度版 日本の100歳以上の人口と現状
・【都道府県ランキング】100歳以上がもっとも多いのは?
・【100歳以上人口の推移】年々増えるご長寿の日本人
・遺伝、性格、血液型は「長寿・短命」に影響する?
・「ご長寿大国」日本の未来
2025年度版 日本の100歳以上の人口と現状
最新の100歳以上人口のデータだっポ。
厚生労働省の発表によると、2025年9月1日時点で100歳を迎えた方(見込み含む)の人数は、5万2,310人(男性:7,964人 女性:4万4,346人)でした。これは前年と比較して4,422人の増加です。
毎年「老人の日(9月15日)」に、その年度に100歳へ到達した・する方に対して、国からお祝い状と記念品が贈呈されています。
ちなみに、2025年時点での100歳以上の人口総数は9万9,763人です。
| 男 | 11,979人 |
|---|---|
| 女 | 87,784人 |
| 総数 | 99,763人 |
この数字は50年ほど前と比較すると、とんでもなく大きな数字です。
「老人福祉法」が制定された昭和38年(1963年)時点では、100歳以上の人口は全国でわずか153人。単純に計算すると、62年で約652倍に増えたことになります。
100歳以上の方の男女比は、2025年時点での100歳以上9万9,763人のうち、男性は1万1,979人(全体の約12%)、女性は8万7,784人(全体の約88%)でした。
圧倒的に女性の割合が高くなっています。これは平均寿命を比較すれば(2024年時点:男性81.09歳、女性87.13歳)納得の結果でしょう。
2025年9月時点での全国最高齢の方は、男性は大正3年(1914年)生まれの静岡県の方で111歳、女性は明治44年(1911年)生まれの奈良県の方で御年114歳となっています。
【都道府県ランキング】100歳以上がもっとも多いのは?
100歳以上の人数は都道府県でどのくらい違いがあるのかな?
厚生労働省が発表しているデータを参考に2025年のランキングを作成しました。100歳以上の方の割合と人数を都道府県で比較します。
| 順位 | 都道府県 | 10万人あたり | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 島根県 | 168.69人 | 1,083人 | 130人 | 953人 |
| 2位 | 高知県 | 157.16人 | 1,031人 | 129人 | 902人 |
| 3位 | 鳥取県 | 144.63人 | 768人 | 86人 | 682人 |
| 4位 | 鹿児島県 | 136.49人 | 2,091人 | 234人 | 1,857人 |
| 5位 | 長野県 | 133.92人 | 2,661人 | 367人 | 2,294人 |
| 6位 | 熊本県 | 132.82人 | 2,254人 | 249人 | 2,005人 |
| 7位 | 山口県 | 125.37人 | 1,606人 | 180人 | 1,426人 |
| 8位 | 長崎県 | 125.16人 | 1,567人 | 139人 | 1,428人 |
| 9位 | 愛媛県 | 122.49人 | 1,563人 | 178人 | 1,385人 |
| 10位 | 大分県 | 121.94人 | 1,323人 | 137人 | 1,186人 |
| 11位 | 新潟県 | 120.91人 | 2,538人 | 275人 | 2,263人 |
| 12位 | 山形県 | 118.60人 | 1,199人 | 178人 | 1,021人 |
| 13位 | 宮崎県 | 118.59人 | 1,225人 | 128人 | 1,097人 |
| 14位 | 山梨県 | 116.18人 | 919人 | 122人 | 797人 |
| 15位 | 佐賀県 | 112.82人 | 889人 | 91人 | 798人 |
| 16位 | 香川県 | 112.43人 | 1,031人 | 141人 | 890人 |
| 17位 | 岩手県 | 112.14人 | 1,284人 | 171人 | 1,113人 |
| 18位 | 徳島県 | 110.95人 | 760人 | 82人 | 678人 |
| 19位 | 和歌山県 | 109.2人 | 961人 | 98人 | 863人 |
| 20位 | 富山県 | 107.32人 | 1,070人 | 91人 | 979人 |
| 21位 | 秋田県 | 107.25人 | 962人 | 105人 | 857人 |
| 22位 | 広島県 | 105.53人 | 2,864人 | 328人 | 2,536人 |
| 23位 | 福井県 | 103.11人 | 762人 | 87人 | 675人 |
| 24位 | 岡山県 | 103.00人 | 1,886人 | 215人 | 1,671人 |
| 25位 | 福島県 | 102.93人 | 1,794人 | 228人 | 1,566人 |
| 26位 | 北海道 | 102.26人 | 5,157人 | 681人 | 4,476人 |
| 27位 | 石川県 | 92.71人 | 1,018人 | 110人 | 908人 |
| 28位 | 奈良県 | 90.12人 | 1,158人 | 139人 | 1,019人 |
| 29位 | 岐阜県 | 89.04人 | 1,706人 | 198人 | 1,508人 |
| 30位 | 京都府 | 87.66人 | 2,209人 | 254人 | 1,955人 |
| 31位 | 静岡県 | 85.77人 | 3,025人 | 388人 | 2,637人 |
| 32位 | 三重県 | 84.69人 | 1,449人 | 185人 | 1,264人 |
| 33位 | 群馬県 | 84.55人 | 1,598人 | 181人 | 1,417人 |
| 34位 | 福岡県 | 84.35人 | 4,295人 | 454人 | 3,841人 |
| 35位 | 青森県 | 82.32人 | 959人 | 80人 | 879人 |
| 36位 | 宮城県 | 81.32人 | 1,828人 | 227人 | 1,601人 |
| 37位 | 沖縄県 | 77.56人 | 1,137人 | 102人 | 1,035人 |
| 38位 | 兵庫県 | 76.99人 | 4,109人 | 506人 | 3,603人 |
| 39位 | 栃木県 | 75.38人 | 1,421人 | 181人 | 1,240人 |
| 40位 | 茨城県 | 74.70人 | 2,096人 | 245人 | 1,851人 |
| 41位 | 滋賀県 | 73.18人 | 1,026人 | 126人 | 900人 |
| 42位 | 神奈川県 | 58.38人 | 5,386人 | 733人 | 4,653人 |
| 43位 | 東京都 | 57.48人 | 8,150人 | 1,084人 | 7,066人 |
| 44位 | 千葉県 | 57.27人 | 3,580人 | 409人 | 3,171人 |
| 45位 | 大阪府 | 55.44人 | 4,855人 | 551人 | 4,304人 |
| 46位 | 愛知県 | 53.00人 | 3,954人 | 518人 | 3,436人 |
| 47位 | 埼玉県 | 48.50人 | 3,556人 | 458人 | 3,098人 |
| 全国 | 80.58人 | 99,763人 | 11,979人 | 87,784人 |
100歳以上の人数比で見ると、やはり人口の多い都道府県が上位です。東京、大阪、愛知、福岡といった大都市を中心に、その周辺も100歳以上の人が多い傾向です。
ただし、大都市圏は人口10万人当たりに占める100歳以上の人の数で見ると順位は高くありません。
たとえば、東京は100歳以上の人口ではトップですが、人口10万人あたりの数は57.48人で全国43位となっています。
反対に、人口10万人あたりの100歳以上の人数で全国トップとなっているのは、島根県でなんと168.69人。
人数自体は1,083人と少ないものの、島根県は高齢化ランキングで8位となっているほど高齢化が進んだ県です。
以下の表をみても、100歳以上の割合が高い都道府県は、やはり高齢化がある程度進んでいる傾向であることがわかります。
| 100歳以上(10万人あたり) | 高齢化率 | |
|---|---|---|
| 島根県 | 1位 | 8位(35.2%) |
| 高知県 | 2位 | 2位(36.6%) |
| 鳥取県 | 3位 | 16位(33.7%) |
| 鹿児島県 | 4位 | 13位(34.2%) |
| 長野県 | 5位 | 20位(32.9%) |
| 熊本県 | 6位 | 23位(32.6%) |
| 山口県 | 7位 | 6位(35.5%) |
| 長崎県 | 8位 | 9位(34.7%) |
| 愛媛県 | 9位 | 10位(34.5%) |
| 大分県 | 10位 | 12位(34.4%) |
※高齢化率は2024年のデータ
【100歳以上人口の推移】年々増えるご長寿の日本人
日本の100歳以上人口は、60年で約602倍に増えたっポ!
昭和38年(1963年)当時、100歳以上の人数は全国でわずか153人でしたが、現在の日本が世界有数の「ご長寿大国」になったのは周知のとおりです。
100歳以上の人の数がこの半世紀でどれくらい増えたのでしょうか。人口の推移を見てみましょう。
| 1963年(昭和38年) | 153人 |
|---|---|
| 1965年(昭和40年) | 198人 |
| 1970年(昭和45年) | 310人 |
| 1975年(昭和50年) | 548人 |
| 1980年(昭和55年) | 968人 |
| 1985年(昭和60年) | 1,740人 |
| 1990年(平成2年) | 3,298人 |
| 1995年(平成7年) | 6,378人 |
| 2000年(平成12年) | 13,036人 |
| 2005年(平成17年) | 25,554人 |
| 2010年(平成22年) | 44,449人 |
| 2015年(平成27年) | 61,568人 |
| 2020年(令和2年) | 80,450人 |
| 2021年(令和3年) | 86,510人 |
| 2022年(令和4年) | 90,526人 |
| 2023年(令和5年) | 92,139人 |
| 2024年(令和6年) | 95,119人 |
| 2025年(令和7年) | 99,763人 |
上記の表は基本5年刻みですが、100歳以上人口の推移は昭和45年(1970年)で前年比を下回ったものの、あとはすべての年で上昇しています。
時代背景的に、生活環境や食料事情、医療の発展などの影響が大きく、年々100歳以上となる人が増えていったと考えられます。
昭和30年代から40年代は、日本はまさに高度経済成長期の真っただ中で、さまざまな生活インフラが整った時期です。
たとえば、国民皆保険の開始は昭和36年(1961年)。この年には電気洗濯機の家庭普及率が50%を突破しています。
さらに、昭和40年(1965年)には電気冷蔵庫の普及率が50%を突破しており、食料の保存事情ひとつとっても、ようやく現在の生活スタイルに近づきつつあった時代だと言えるでしょう。
時代が進むにつれ、こうした生活環境や社会インフラの充実と医療技術はますます発展し、長生きできる確率が格段に上がっていきました。
日本人の平均寿命は伸びていますが、子どもの数が少なくなったことから、平成に入ると日本は少子高齢化が顕著になり、高齢者を支える現役世代の減少が問題となっています。
遺伝、性格、血液型は「長寿・短命」に影響する?
長寿を科学的に研究したおもしろいレポート結果があるっポ。
誰もが100歳以上生きることが現実味を帯びてきている以上、できるだけ健康長寿で過ごしたいですよね。
ところで、長寿は家系と関係しているのでしょうか。
ニッセイ基礎研究所の長寿科学研究に関するレポートによると、寿命そのものに与える遺伝の影響は約20~30%ほどで、70%以上は生活習慣などの環境的原因によるものが大きいとのことです。
この調査は北欧で行われた「一卵性双生児の追跡調査」によって判明したもので、長寿に大きく関係するのは体質や遺伝よりも、普段からの生活習慣や環境的な要因が大きいと科学的に証明されつつあります。
さらに「性格」が長寿に影響するという結果もあるようです。
世界中で行われているさまざまな調査結果を複合すると、ご長寿には「明るい、呑気、楽天的」な性格の人が多く、反対に競争的で攻撃的といった性格の人は短命の傾向にあるとのことです。
「性格と長寿の関係」以外にも、「血液型と長寿の関連性」というおもしろい調査結果が紹介されています。
日本では血液型と性格を関連付けて考えることも多いため、もしかしたらこの結果は、性格的な傾向と長寿の関係性を間接的に裏付けるものなのかもしれません。
日本人の100歳以上の方を血液型別にその割合を調べてみると(調査人数269名分)、A型34%、O型29%、B型29%、AB型8%だったそうです。
| 日本人全体 | 100歳以上 | |
|---|---|---|
| A型 | 40% | 34%↓ |
| B型 | 20% | 29%↑ |
| O型 | 30% | 29%↓ |
| AB型 | 10% | 8%↓ |
日本人全体で見るとA型は40%、O型30%、B型20%、AB型10%ですから、比較するとA型やAB型が短命で、B型が長寿傾向にあるということになりますね。
「ご長寿大国」日本の未来
日本はご長寿大国ということもあり、高齢者の増加傾向は世界を先行しています。
2025年現在、100歳以上の方の人数は9万9,763人。今のペースだと10万人を突破する日も遠くはありません。
日本の高齢化率のピークはまだまだ先です。100歳以上の方が生き生きと暮らすためには、社会全体で高齢者を支える仕組みづくりを考えていく必要があります。
まさに未知の超高齢社会へと突入する日本、豊かな老後を過ごせる社会が実現するといいですね。
こちらもおすすめ
おすすめ事業所情報
新着記事
ハートページ誌は、全国約70市区・約100万部を発行する業界最大級の介護情報誌。20年を超える歴史(2001年創刊)、カバーするエリアの広さ、発行部数、各自治体や連絡協議会と連携し制作された信頼性の高さで、介護に関わるみなさまより高い評価を得ています。
ハートページナビでは、介護情報を専門に扱うサイトとして、介護に関わる皆さまに必要な情報、役立つ情報などを掲載しています。