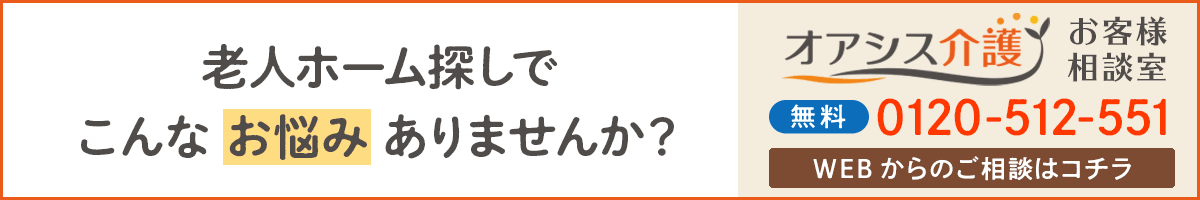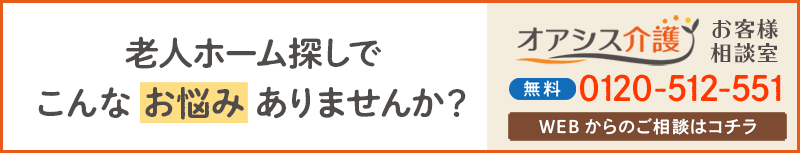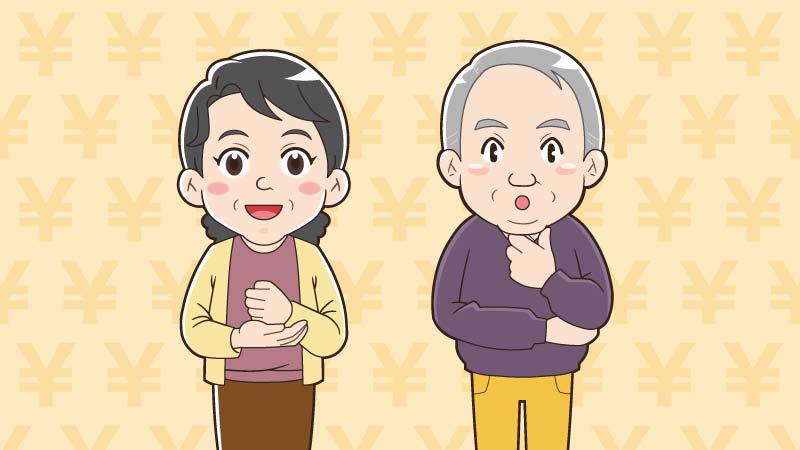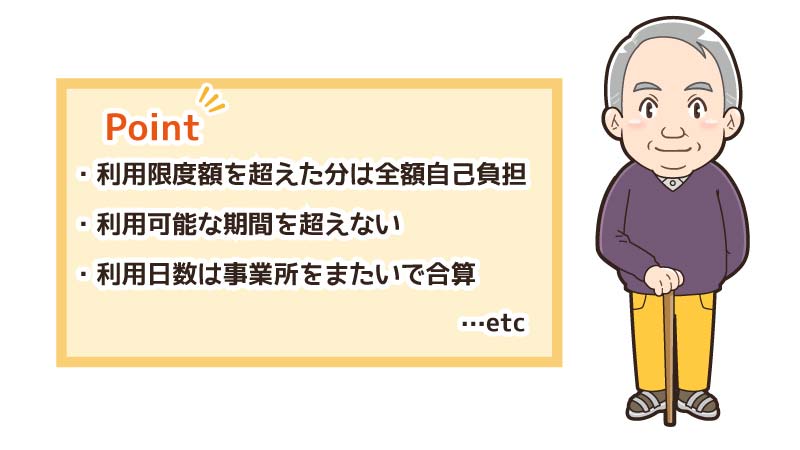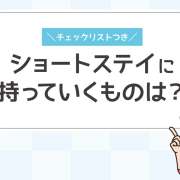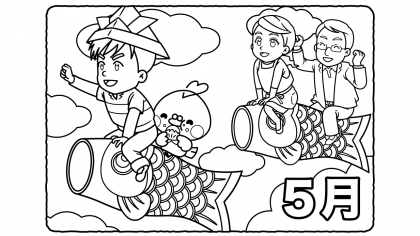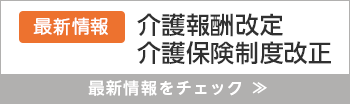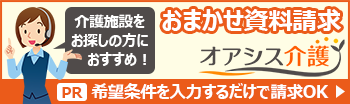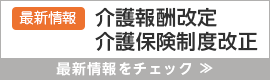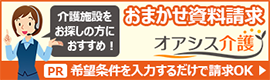ロングショートステイは、ショートステイを“ロング”で利用することを指します。ロングショートステイにはいくつかの注意点があり、安心して利用するめには事前の理解が必要です。
ここでは、利用期間のルールや、介護保険が適用される日数の目安、費用などについて、詳しく解説します。ぜひ最後までお読みください。
・ロングショートステイとは
・ロングショートステイの利用期間
・ショートステイの料金表と利用日数の目安
・ロングショートステイを利用する方法
・ロングショートステイのケアプラン例
・ロングショートステイの注意点
・ロングショートステイを希望する方はケアマネに相談を
ロングショートステイとは
ロングショートステイとは、ショートステイを長期に渡り利用することです。ショートステイは介護サービスのひとつで、高齢者の孤立感の解消や家族の介護負担軽減などを目的に、施設に短期間だけ宿泊します。
ショートステイの利用期間は人それぞれですが、数日から2週間程度が一般的です。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの報告書によると、連続利用の日数は1週間以内が74%、2週間以内は84.4%です。
2週間以上の長期に渡り利用する方もいますが、ショートステイはその名の通り、短期的に滞在するサービスとなります。そのため、老人ホームへの入居のように長期的に暮らせるわけではありません。
ロングショートステイの利用期間
ショートステイは短期間の宿泊を想定した介護サービスです。そのため、ロングショートステイを希望しても好きなだけ滞在できるわけではありません。
介護保険ではショートステイの利用期間に以下の制限があります。
- 介護認定期間(有効期間)の半数を超えた利用はできない
- 連続で利用できる日数は30日まで
介護認定期間は要介護認定の有効期間のことです。たとえば、介護認定期間が180日間の場合は、最大90日間ショートステイを利用できます。かつ、1回あたりの連続利用は30日までです。
もし、長期で利用する方が増えてしまうと、限られたショートステイの枠が塞がれてしまいます。本当にサービスを必要とする方が利用できなくなる事態を避けるため、このような決まりがあるのです。
ショートステイの料金表と利用日数の目安
介護保険サービスは1~3割の負担で利用できますが、要介護度ごとに支給限度額が設定されています。支給限度額を超えた分は全額が自己負担になるため、費用負担を膨らませないためには限度額内に抑える必要があります。
支給限度額内でショートステイを利用する場合は、以下の日数が目安です。この日数を超えると限度額をオーバーする可能性があります。
| 従来型個室・多床室(1日あたり) | ユニット型(1日あたり) | 支給限度額 | 利用日数の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 451円 | 529円 | 5,032円 | 6日程度 |
| 要支援2 | 561円 | 656円 | 10,531円 | 11日程度 |
| 要介護1 | 603円 | 704円 | 16,765円 | 17日程度 |
| 要介護2 | 672円 | 772円 | 19,705円 | 20日程度 |
| 要介護3 | 745円 | 847円 | 27,048円 | 28日程度 |
| 要介護4 | 815円 | 918円 | 30,938円 | 30日程度 |
| 要介護5 | 884円 | 987円 | 36,217円 | 30日程度 |
*1単位10円、1割負担で計算
上記の日数はあくまで目安です。実際の料金は、サービス加算やその他サービスの利用状況などによって設定されるため、利用できる日数は前後します。
また、上記の料金表は介護サービスの基本料金です。このほかに介護保険が適用されない費用として、食費やおむつ代なども別途必要です。
ロングショートステイを利用する方法
ショートステイは介護保険サービスのひとつです。そのため、まずは要介護認定を受ける必要があります。
認定を受けたら、担当のケアマネジャーにショートステイをロングで使いたい旨を相談しましょう。
以下は、ロングショートステイを利用するまでの主な流れです。
- 要介護認定を受ける
- ケアマネジャーにロングショートステイの利用を相談する
- ケアマネジャーがケアプラン・理由書を作成する
- ロングショートステイの利用を開始する
ショートステイなどの介護保険サービスを利用するためには、ケアプランが必要です。ケアプランは一般的にケアマネジャーが作成し、ご本人やご家族の希望も盛り込まれます。
ロングショートステイに必要な理由書とは
ショートステイは介護認定期間(有効期間)の半数を超えた利用ができませんが、必要だと認められた場合はその限りではありません。
以下のようなやむを得ない事情があると、利用可能な期間を超えて滞在できる可能性があります。
- 在宅介護が困難になった
- 同居の家族が病気や高齢などで介護できない
- 一人暮らしの継続が困難になった
など
利用可能な期間を超えてショートステイに滞在するときは、長期利用の必要性を明記した理由書の提出が必要です。理由書はケアマネジャーが作成し、お住いの自治体へ提出します。
ロングショートステイのケアプラン例
ここでは、ロングショートステイを利用するときのケアプラン例を紹介します。
要介護2のAさん(夫婦二人暮らし)
妻と二人暮らしのAさんは84歳。要介護2で短期記憶の低下や見当識障害がみられます。
あるとき、主な介護者である妻が長期で入院することになり、Aさんの在宅生活の継続が困難になったため、ロングショートステイの利用を希望されました。
見守りのある環境であれば在宅生活の継続は可能ですが、介護者である妻の入院により介護力が不十分のため、安全確保の観点からショートステイを長期で利用していただき、日常生活を包括的に支援いたします。
慣れない場所での生活に戸惑われる可能性もあり、ショートステイでは日常生活動作の維持・向上を図りつつ、ご本人の意思に寄り添いながら支援いたします。
日常生活動作を維持向上し、妻と自宅で生活したい。
<長期目標>
在宅生活に復帰できる。
<短期目標>
見守りのなかで、食事や排泄など自立した生活を送れる。
<サービス内容>
ショートステイの長期利用、日常生活動作の見守り支援、機能訓練への参加など。
慣れない場所で不安を感じず生活したい。
<長期目標>
環境に慣れ、混乱や不安を最小限に、穏やかに過ごせる。
<短期目標>
生活リズムを整えたり馴染みの関係を構築したりできる。
<サービス内容>
生活リズムを確立するための個別支援、利用者間の介入など。
ロングショートステイの注意点
ロングショートステイを検討するときには、以下の点に注意しましょう。
・利用可能な期間を超えない
・利用日数は事業所をまたいで合算される
・福祉用具貸与を併用できない
・訪問診療の制限がある
・生活保護が停止される可能性がある
ロングショートステイで注意すべき点について、それぞれ解説します。
利用限度額を超えた分は全額自己負担になる
介護保険サービスの利用が利用限度額を超えると、超えた分は全額自己負担になります。ここには、デイサービスや訪問介護など他の介護サービス料金も含まれるため、合算額の確認が必要です。
利用限度額は以下を参考にしてください。
| 要支援1 | 5,032円 |
|---|---|
| 要支援2 | 10,531円 |
| 要介護1 | 16,765円 |
| 要介護2 | 19,705円 |
| 要介護3 | 27,048円 |
| 要介護4 | 30,938円 |
| 要介護5 | 36,217円 |
*1単位10円、1割負担で計算
利用可能な期間を超えない
ショートステイは介護認定期間(有効期間)の半数を超えて利用できず、連続利用できる日数は最大30日です。
ただし、介護保険が適用される日数は要介護ごとに異なり、上限を超えた分は全額が自己負担になります。
以下は、利用限度額を超えずにショートステイを利用できる日数の目安です。ただし、サービス加算や地域などにより目安となる日数は前後します。
| 要支援1 | 6日程度 |
|---|---|
| 要支援2 | 11日程度 |
| 要介護1 | 17日程度 |
| 要介護2 | 20日程度 |
| 要介護3 | 28日程度 |
| 要介護4 | 30日程度 |
| 要介護5 | 30日程度 |
利用日数は事業所をまたいで合算される
複数の事業所をまたいでショートステイを連続利用した場合も、継続利用として扱われます。
たとえば、A事業所で8日間、日を空けずにB事業所で5日間ショートステイを利用すると、連続利用は13日間です。
同じ事業所で30日間ショートステイを利用したあとに、31日目から別の事業所で再びショートステイを利用しても、連続利用とみなされて上限の30日をオーバーすることになります。
上限の30日を超えて利用したいときは、以下の方法を検討しましょう。
- 1日だけ全額自己負担で利用する
- 一度自宅に戻り、一定期間をあけてから再びショートステイを利用する
福祉用具貸与を併用できない
福祉用具貸与は在宅生活を支援する介護サービスのため、ショートステイ滞在中の利用は想定していません。福祉用具貸与で借りた車椅子などはショートステイ先に持ち込めないので注意しましょう。
車椅子や介護ベッドなどはショートステイ先に用意されています。ショートステイが用意する福祉用具がご本人に合うか心配な方は、前もって施設やケアマネジャーに相談しておくと安心です。
訪問診療の制限がある
ショートステイの利用中は、基本的にその施設の担当医師が診察します。
自宅で訪問診療を受けていた方はショートステイでも引き続き訪問診療を受けられますが、自宅で診察を受けてから30日を超えると訪問診療を受けられなくなります。
30日を超えて訪問診療を受けたいときは、一度自宅に戻り診察を受けることが必要です。
継続的な治療や服薬管理が必要な方は、事前に主治医やケアマネジャー、ショートステイ先に相談しておきましょう。
生活保護が停止される可能性がある
生活保護と年金の両方を受け取っている方は、ロングショートステイの利用により生活保護が停止される可能性があります。
生活保護の受給者には、ショートステイでの食費や居住費を軽減できる制度があり、費用負担を抑えることが可能です。
しかし、ショートステイでの費用が年金額を下回ると、年金だけで生活費を賄えると判断され、生活保護が止められるおそれがあります。
ロングショートステイを希望する方はケアマネに相談を
ロングショートステイは、ショートステイを長期に渡り利用することです。ただし、介護認定期間(有効期間)の半数を超えた利用や、連続30日以上の利用はできません。上限を超えて利用するときは理由書の提出などが必要です。
ショートステイの長期利用は、費用負担が非常に大きくなる可能性があります。介護保険サービスは要介護度ごとに支給限度額が決められているため、上限額を確認しながら利用しましょう。
ロングショートステイを検討している方は、しっかりと仕組みを理解し、ケアマネジャーによく相談したうえで利用するようにしてください。
ハートページナビでは地域の介護事業所を一覧から探せます
こちらもおすすめ
おすすめ事業所情報
新着記事
ハートページ誌は、全国約70市区・約100万部を発行する業界最大級の介護情報誌。20年を超える歴史(2001年創刊)、カバーするエリアの広さ、発行部数、各自治体や連絡協議会と連携し制作された信頼性の高さで、介護に関わるみなさまより高い評価を得ています。
ハートページナビでは、介護情報を専門に扱うサイトとして、介護に関わる皆さまに必要な情報、役立つ情報などを掲載しています。