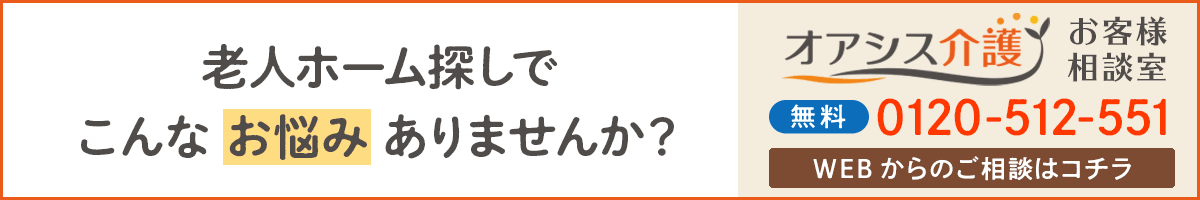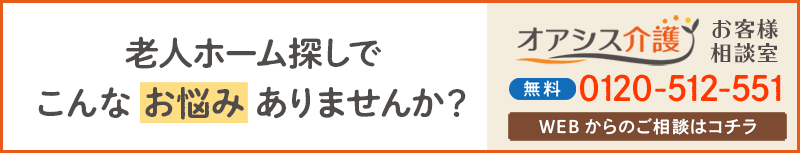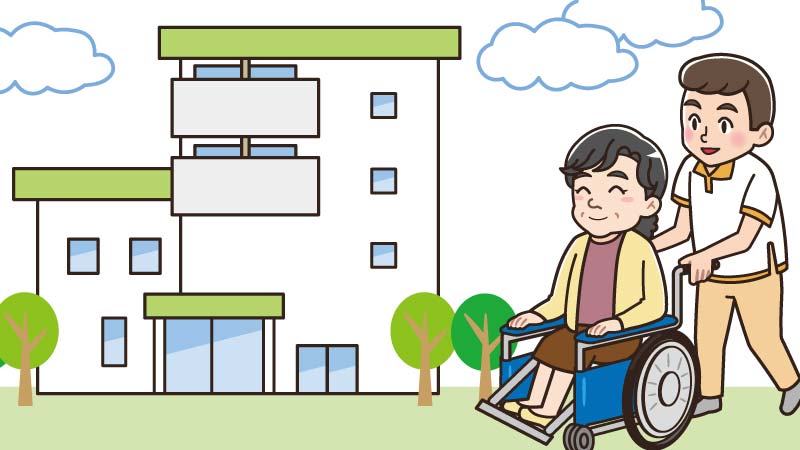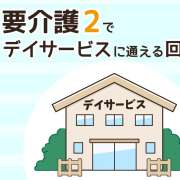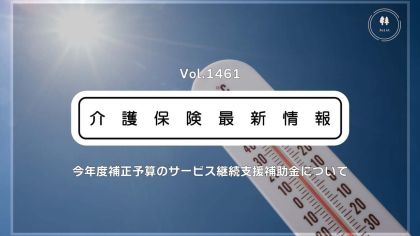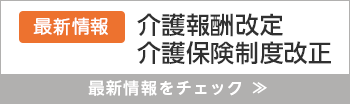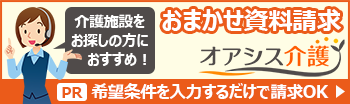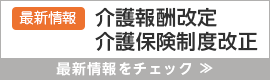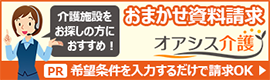要介護5は要介護度のなかでもっとも重い状態です。要介護5での在宅介護は無理なのでしょうか。
ここでは、要介護5で在宅介護をしている人の割合、できるだけ無理なく在宅介護を続ける方法、限界を感じたときの対処法、受け取れる給付金・払戻金などについて、ケアマネジャーが詳しく解説します。
・要介護5で在宅介護は無理?
・要介護5で在宅介護を続けるためには?
・要介護5のケアプラン例
・要介護5の在宅介護に無理を感じたら、施設入居の検討を
・「要介護5の在宅介護は無理」となる前に相談を
要介護5の状態とは?
要介護5は、もっとも介護を必要とする状態だっポ。
要介護5は、要介護状態区分のうちもっとも高く、常に介護を必要とする状態です。寝たきりの方や、認知症により意思疎通が困難な方など、介護がなければ日常生活をほぼ送れない方が該当します。
要介護5の認定者には、以下のような状態の方がいます。
- 1日の多くをベッドの上で過ごす
- 座位が保てない
- 歩けない、立ち上がれない
- 排泄は全介助で、おむつを使用している
- 胃ろうや経管栄養をしている
- コミュニケーションが難しい
- 不潔行為や自傷他害などの著しい周辺症状(問題行動)が見られる
など
要介護5で在宅介護は無理?
要介護5で在宅介護をしている世帯の割合も紹介するっポ。
要介護5で在宅介護できるかどうかは、その方の状態や家族の状況などにより異なります。そのため、一概に「できる」とも「無理」とも言えません。
要介護5は、介護なしに日常生活を送ることがほぼ不可能な状態です。介護の環境を整えて在宅介護を継続しているご家庭もありますが、ご家族の負担が大きくなり現実的に困難になってしまうケースも少なくありません。
要介護5の在宅介護の割合
要介護5で在宅介護をしている方はどのくらいいるのでしょうか。厚生労働省の資料によると、どの世帯構造(一人暮らし、核家族、三世代)でも、要介護5の在宅介護の割合がもっとも低くなっています。
| 単独世帯 | 核家族世帯 | 三世代世帯 | |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 17.5% | 13.9% | 12.2% |
| 要支援2 | 26.1% | 15.2% | 13.9% |
| 要介護1 | 18.9% | 19.2% | 20.3% |
| 要介護2 | 16.5% | 19.7% | 20.4% |
| 要介護3 | 9.0% | 13.1% | 14.4% |
| 要介護4 | 5.9% | 9.4% | 9.3% |
| 要介護5 | 3.3% | 7.6% | 7.9% |
要介護5の方がいる世帯はいずれも8%未満で、平均すると6%の世帯が要介護5の方の在宅介護をしている状況です。
そもそも要介護5の認定者は他の介護度に比べて少なめですが、それでも介護の必要度が高い人ほど、施設や病院などに入る傾向があると読み取れます。
また、在宅介護に要する時間をみると、要介護5では「ほとんど終日」と回答した割合が63.1%で、「半日程度」の17.2%を合わせると80.3%という結果でした。
| 半日程度 | ほとんど終日 | |
|---|---|---|
| 要支援1 | 4.1% | 3.1% |
| 要支援2 | 1.7% | 3.7% |
| 要介護1 | 8.9% | 11.8% |
| 要介護2 | 12.3% | 17.0% |
| 要介護3 | 21.9% | 31.9% |
| 要介護4 | 20.0% | 41.2% |
| 要介護5 | 17.2% | 63.1% |
要介護5の方の在宅介護では、8割以上の方が半日~1日の大半を介護に充てている状態です。この結果からも、要介護5の方を介護する家族の負担がいかに大きいかわかります。
要介護5では在宅介護の継続が難しく、施設への入居を選択するケースも多いのです。
要介護5でかかる費用
要介護5は介護なしでの日常生活がほぼ不可能なため、在宅介護を継続するなら介護サービスの利用が欠かせません。
介護保険サービスにかかる費用には、要介護ごとに支給限度額が設定され、その範囲内であれば所得に応じて1~3割の負担でサービスを利用できます。
要介護5の支給限度額は1カ月あたり約36万2,170円で、1割負担であれば約36,217円が上限額です。
| 要支援1 | 5,032円 |
|---|---|
| 要支援2 | 10,531円 |
| 要介護1 | 16,765円 |
| 要介護2 | 19,705円 |
| 要介護3 | 27,048円 |
| 要介護4 | 30,938円 |
| 要介護5 | 36,217円 |
*1割負担・1単位10円で計算
これらの支給限度額を超えた分は全額自己負担となります。
介護サービスでかかる費用以外にも、おむつ代や介護食代などが必要です。また、要介護5に認定された方は何らかの医療を必要とすることも多く、医療費などもかかります。
要介護5で在宅介護を続けるためには?
相談できる相手がいると、精神的な負担を減らせるっポ。
要介護5の方の在宅介護では家族に大きな負担がかかりますが、先述したデータによると6%程度の世帯が在宅介護を続けています。
要介護5の認定を受けてもできる限り在宅介護を続けたいという方は、以下のポイントを意識してみてください。
・介護保険サービスを利用する
・保険外サービスを利用する
・勤務先の制度を活用する
・給付金・払い戻し制度に申し込む
要介護5で在宅介護を続けるためのポイントを、以下で詳しく紹介します。
ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談する
要介護5の方の在宅介護では家族の負担が大きくなるため、頼れる人に相談しましょう。
まず身近なところでは担当のケアマネジャーです。ケアマネジャーは、ご本人の状態やご家族の思いなどを聞いたうえでケアプランを立て、必要に応じて見直しもしてくれるため、要介護5の方の在宅介護でも適切に対応してくれます。
高齢者に関する相談は地域包括支援センターでも可能です。介護の相談を総合的にできるほか、適切なサービスや制度を紹介してもらえます。相談先に困ったときは頼ってみるとよいでしょう。
介護保険サービスを利用する
要介護5での在宅介護の負担を軽減するためには、介護サービスを上手に組み合わせて利用することもポイントです。
要介護5ではすべての介護保険サービスを利用でき、在宅介護では以下のサービスを受けられます。
自宅を訪問するサービス
訪問介護
ヘルパーが利用者の自宅を訪問し、身体介護、生活援助、通院等乗降介助を行う
訪問看護
看護師や理学療法士などが利用者の自宅を訪問し、療養上の世話やリハビリテーションを行う
訪問入浴介護
利用者の自宅に簡易浴槽を持ち込み、入浴介助を行う
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが利用者の自宅を訪問し、健康管理の助言や療養の指導を行う
訪問リハビリテーション
理学療法士や言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、リハビリテーションを行う
夜間対応型訪問介護
夜間に訪問介護サービスを行う地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
状況に応じて利用者の自宅を訪問し、定期的な巡回や随時対応などのサービスを行う地域密着型サービス
施設に通うサービス
デイサービス
利用者が施設に通い、食事の提供やレクリエーションなどを受ける
デイケア
利用者が施設に通い、リハビリテーションなどを受ける
宿泊するサービス(ショートステイ)
短期入所生活介護
利用者が短期間施設に宿泊し、日常生活上の支援やレクリエーションなどを受ける
短期入所療養介護
利用者が短期間施設に宿泊し、療養生活上のケアや機能訓練などを受ける
通い・訪問・宿泊を組み合わせたサービス
小規模多機能型居宅介護
ひとつの事業所が、通い、訪問、泊りのサービスを行う
看護小規模多機能型居宅介護
上記に加えて、訪問看護サービスも行う
福祉用具レンタル・購入のサービス
福祉用具貸与
介護ベッドや車椅子などの福祉用具をレンタルする
特定福祉用具販売
入浴補助用具や簡易浴槽などの福祉用具を購入する
住宅リフォームのサービス
住宅改修費
介護のために住宅をリフォームする
保険外サービスを利用する
介護保険サービスでできることには制限があるため、家族の負担を軽減しきれない可能性があります。そのようなときは、保険外サービスの利用がおすすめです。
保険外サービスは10割負担で費用がかかってしまいますが、必要に応じて利用すると介護の負担をより軽減できます。
たとえば、以下のような保険外サービスがあります。
高齢者見守りサービス
高齢者の安否確認や緊急時の対応などを行うサービス。訪問型、センサー型、緊急対応型などがある
配食サービス
決まった時間帯や曜日に食事を届けるサービス。安否確認も兼ねている
介護タクシー
自力での移動が難しい方に向けたタクシー。車椅子やストレッチャーのまま乗れる車両もある
訪問理美容
理美容師が利用者の自宅を訪問し、散髪や顔そりなどを行う
勤務先の制度を活用する
要介護5では介護にかかる時間がほぼ終日となるケースも多く、介護と仕事の両立に悩み辞職を考えるご家族も少なくありません。
しかし、離職すると安定した収入を得られず、再就職が困難になる可能性もあります。
介護離職を決断する前に、ぜひ介護休業制度を活用してください。介護休業制度は育児・介護休業法に基づく制度で、一定の条件を満たせば最大93日間の休業が可能です。
介護休業制度では、以下のように労働時間の制限などができます。
| 介護休業 | 対象家族1人につき通算93日、3回まで休業できる |
|---|---|
| 介護休暇 | 対象者1人で年5日、2名以上で年10日を、時間単位あるいは1日単位で休暇できる |
| 所定外労働の制限 | 残業を免除できる |
| 時間外労働の制限 | 1カ月で24時間、1年で150時間を超える時間外労働を制限できる |
| 深夜業の制限 | 22時から翌5時までの労働を制限できる |
| 短時間勤務等の措置 | フレックスタイム、短時間勤務、時差出勤、介護費用の助成など、利用できる制度は企業により異なる |
介護休業制度のほか、介護支援を目的とした制度を独自に設ける会社もあります。
辞職という選択は、介護が終わったあとのご家族の人生に関わります。まずは制度を活用し、離職しない道を探ってみてください。
給付金・払い戻し制度に申し込む
要介護5では、介護サービス費、おむつ代、医療費などにより、ご家族の金銭的負担が大きくなる可能性があります。介護のために仕事をセーブしたり辞職したりすると収入が減少し、金銭的な負担はより深刻になります。
介護による金銭的な負担を軽くするためには、以下の給付金・払い戻し制度をご活用ください。
介護休業給付金
介護休業の取得により賃金が80%未満に低下するなどの要件を満たしたとき、ハローワークへの申請で支給される
家族介護慰労金
要介護度が高い、介護保険サービスを利用していないなどの条件を満たした方の家族に対し、年額10万円程度が支給される。条件は市町村により異なる
高額介護サービス費制度
介護保険サービスの利用が負担限度額を超えたときに、超過分が払い戻される
障害者控除
障害者手帳がなくても、精神または身体に障害のある65歳以上・要介護1以上の方は障害者控除を受けられる可能性があるため、居住する市町村に確認する
要介護5のケアプラン例
半身まひと言語障害がある要介護5の方のケアプラン例を紹介するっポ。
ケアプランは一人ひとりに合わせた内容で作成されますが、ここでは一例として要介護5のケアプラン例を紹介します。
半身まひと言語障害があるAさん
要介護5のAさん(85歳・女性)は、要支援1の夫、娘夫婦と同居しています。脳梗塞の後遺症により半身まひと言語障害があり、ベッド上での生活が中心です。食事や排泄など日常生活のほぼすべてで介助の手がかかります。
主介護者の娘は週3でパートに出ており、その間はデイサービスを利用。また、排泄や体位交換などの日常生活上の支援は訪問介護で、不安のある嚥下状態の確認は訪問看護を利用しています。
娘が不在にする日は、ご本人に適した食事形態での配食サービスも利用しています。
しかし、要介護5のAさんの夫も要支援1で、今後は介護負担がより大きくなるかもしれません。不安を感じるようになり、定期的にショートステイも利用することにしました。
| 介護サービス | 利用回数/月 | 利用時間/回 | 自己負担額/月 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 44回 | 20分以上30分未満 | 10,736円 |
| 通所介護 | 12回 | 6時間以上7時間未満 | 12,096円 |
| 訪問看護 | 4回 | 30分以上1時間未満 | 3,292円 |
| 短期入所生活介護 | 4回(2日) | ― | 3,536円 |
| 居宅療養管理指導(医師) | 2回 | ― | 515円 |
| 居宅療養管理指導(薬剤師) | 4回 | ― | 518円 |
| 福祉用具貸与(ベッド) | ― | ― | 1,000円 |
| 福祉用具貸与(サイドレール2本) | ― | ― | 50円 |
| 福祉用具貸与(床ずれ防止用具) | ― | ― | 1,000円 |
| 福祉用具貸与(体位変換器2つ) | ― | ― | 300円 |
| 福祉用具貸与(車椅子) | ― | ― | 700円 |
| 福祉用具貸与(スロープ) | ― | ― | 500円 |
| 自己負担額の合計 | 34,243円 | ||
*1単位10円、1割負担で計算
| 配食サービス | 24回 | ― | 20,688円 |
|---|---|---|---|
| 保険外サービス費の合計 | 20,688円 | ||
要介護5の在宅介護に無理を感じたら、施設入居の検討を
「施設はまだ早い」と思っていても、早めに探しておけばいざというときに安心だっポ。
要介護5の方の介護では、身体的にも精神的にも負担が大きくなる可能性があります。無理な在宅介護を続け、共倒れになってしまっては元も子もありません。
在宅介護で限界を感じる前に、施設への入居も検討しておくと、いざというときに安心です。
以下は、一般的な施設入居の流れです。
2.老人ホームの情報を集める
3.気になる施設を見学・体験入居する
4.入居を申し込む
1.ケアマネジャーに相談する
まずは担当のケアマネジャーに相談してください。希望に沿った施設の提案や、必要に応じてケアプランの見直しをしてもらえます。
地域包括支援センターや施設の紹介会社などでも相談できますが、担当ケアマネジャーに声をかけておくと、その後の流れがスムーズです。
2.老人ホームの情報を集める
老人ホームにはたくさんの種類があり、それぞれ特徴や入居条件が異なります。認知症や医療依存度の程度、経済状況、ご本人やご家族の希望などに合わせて慎重に検討してください。
以下は、要介護5の方が入居できる主な施設です。
有料老人ホーム
要介護5の方が入居できるのは、介護付き有料老人ホームと住宅型有料老人ホームです。
介護付き有料老人ホームには24時間の介護やケアマネジャーの配置があり、サービスは施設内でほぼ完結します。一方、住宅型有料老人ホームは、在宅介護と同じように訪問介護などを利用しながら生活する施設です。
有料老人ホームは、施設によってサービス内容や入居条件が大きく異なるため、詳細は各施設に確認が必要です。
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームは原則として要介護3以上で入居できる施設です。長期的に入居でき、終の棲家として多くの方に選ばれています。
経済的に不安のある方も入居しやすい施設ですが、入居を希望する人が多いため、空きがでるまで長期間待つことも少なくありません。
介護医療院
介護医療院は、医療と介護の両方を必要とする方が、日常生活を送りながら長期に渡り療養できる施設です。病院から退院した方、医療ケアが欠かせない方でも、安心して療養生活を送れます。
3.気になる施設を見学・体験入居する
気になる施設が見つかったら、実際に見学するとよいでしょう。
設備、清潔さ、におい、雰囲気、スタッフの対応、入居者の様子などを確認し、「良さそうだな」と思ったら、体験入居がおすすめです。
食事の内容、介助のタイミング、夜間の対応など、見学では分からなかった部分を知ることができます。
特別養護老人ホームの場合は、ショートステイを利用するとその施設での暮らしを体験できます。ただし、通常の入居者とはフロアが違うなどのケースもあるため、詳しくはケアマネジャーや施設に確認が必要です。
4.入居を申し込む
納得できる施設が見つかったら、入居を申し込みます。施設によっては住所変更などが必要なケースもあるため、事前に担当ケアマネジャーや入居先の担当者に確認しておくと安心です。
「要介護5の在宅介護は無理」となる前に相談を
要介護5は要介護度のなかでもっとも重く、介護なしには日常生活を送れない状態です。
要介護5の方の在宅介護ではご家族の負担が大きくなるため、介護サービスの利用や介護休業制度、給付金・払い戻し制度などを活用すると、身体的・精神的・金銭的な負担を軽減できます。
ご家族が倒れてしまっては元も子もありません。ご家族だけで介護を抱え込まず、「在宅介護はもう無理」と限界を迎える前に周囲に相談し、無理のない介護を目指してください。
こちらもおすすめ
おすすめ事業所情報
新着記事
ハートページ誌は、全国約70市区・約100万部を発行する業界最大級の介護情報誌。20年を超える歴史(2001年創刊)、カバーするエリアの広さ、発行部数、各自治体や連絡協議会と連携し制作された信頼性の高さで、介護に関わるみなさまより高い評価を得ています。
ハートページナビでは、介護情報を専門に扱うサイトとして、介護に関わる皆さまに必要な情報、役立つ情報などを掲載しています。