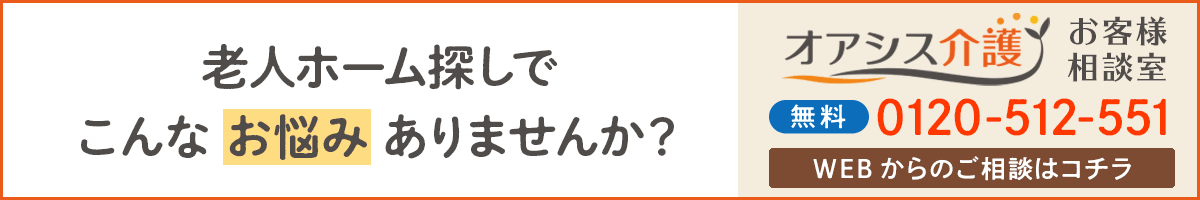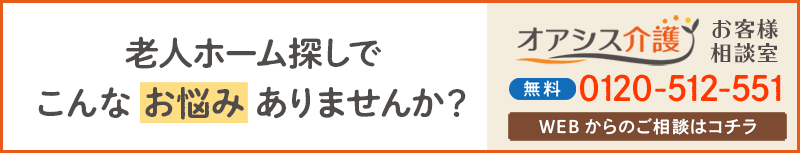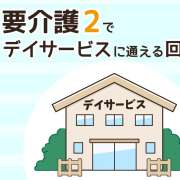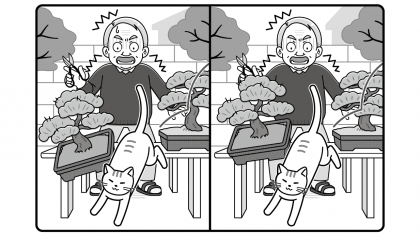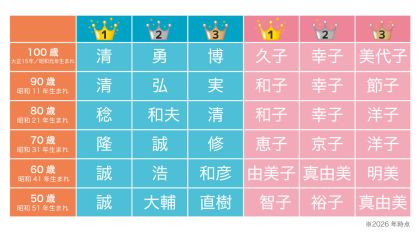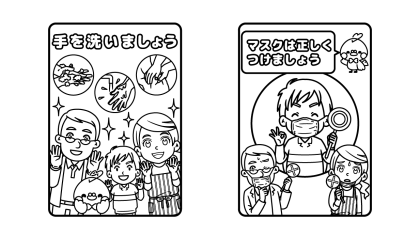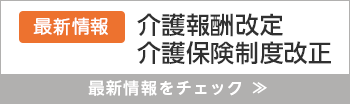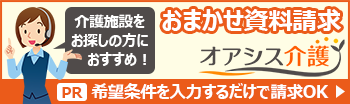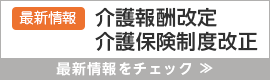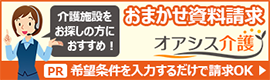要介護5は要介護度のなかでもっとも重く、介護保険サービスの活用が欠かせない状態です。
この記事では、要介護5の状態や、利用できる介護保険サービス、ケアプラン例、費用の目安、給付金などについて、ケアマネジャーが解説します。
ご家族が要介護5に認定されたとき、または事前の備えとして、ぜひ参考にしてください。
・要介護5の状態とは
・要介護5と要介護4の違い
・要介護5の人が介護を必要とするようになった原因
・ケアマネジャーが知る要介護5に認定されたケース
・要介護5の介護期間
・要介護5で利用できる介護保険サービス
・要介護5のケアプラン例
・自己負担額はどのくらい?要介護5の支給限度額
・要介護5に関するよくある質問
・要介護5のまとめ
要介護5の状態とは
要介護5はもっとも介護が必要な状態だっポ。
要介護5は、介護なしでの日常生活がほぼ不可能な状態です。昼夜問わず目を離せない方や寝たきりの方などが要介護5に該当します。
以下のような動作はほとんどできません。
- 料理や清掃など生活に必要な動作
- 食事や排泄などの基本的な動作
- 立ち上がりのような複雑な動作
- 歩行のような移動の動作
要介護5では、理解力や判断力も非常に乏しく、コミュニケーションが難しい方も多くいます。
要介護度のうちもっとも介護が必要な状態であり、要介護認定の基準に当てはめると、要介護認定等基準時間が110分以上、またはこれに相当する状態を指します。
要介護認定等基準時間は、以下の行為にかかる介護の手間を時間に換算したものです。ただし、実際の介護でかかった時間とは異なります。
| 行為の区分 | 具体的な内容 | |
|---|---|---|
|
直接生活介助 |
食事 | 食事にまつわる行為 |
| 排泄 | トイレ・排泄にまつわる行為 | |
| 移動 | 移動にまつわる行為 | |
| 清潔保持 | 入浴、衣類の着脱等 | |
| 間接生活介助 | 洗濯、掃除等の家事援助等 | |
| BPSD 関連行為 | 徘徊に関する探索、不潔な行為に関する後始末等 | |
| 機能訓練関連行為 | 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練 | |
| 医療関連行為 | 輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助 | |
要介護度ごとの要介護認定等基準時間は、以下のとおりです。
| 要介護認定等基準時間 | |
|---|---|
| 非該当 | 25 分未満 |
| 要支援1 | 25分以上32分未満 またはこれに相当する状態 |
| 要支援2 | 32分以上50分未満 またはこれに相当する状態 |
| 要介護1 | |
| 要介護2 | 50分以上70分未満 またはこれに相当する状態 |
| 要介護3 | 70分以上90分未満 またはこれに相当する状態 |
| 要介護4 | 90分以上110分未満 またはこれに相当する状態 |
| 要介護5 | 110分以上 またはこれに相当する状態 |
要介護5と要介護4の違い
要介護4と要介護5にはどんな違いがあるのかな?
要介護4は、介護なしでの日常生活が難しい状態です。何らかのサポートによりできる行為もありますが、たとえば、自力での移動が困難なため車椅子を使ったり、座った状態を保てなかったりします。寝たきりの方も少なくありません。
認知機能が低下し、不潔行為や徘徊などの周辺症状で目が離せなくなることもあるでしょう。
要介護5は、要介護4よりもさらに能力が低下し、介護なしでの日常生活が限りなく困難な状態です。
たとえば、身体・認知機能の低下により、食事は用意から摂取まで全面的に他者の力が必要です。寝たきり状態の方も多く、外出も困難になります。医療的な管理が必要なケースも多いでしょう。
要介護5の人が介護を必要とするようになった原因
要介護5の人はどんな原因で介護が必要になったのかな?
| 第1位 | 脳血管疾患(脳卒中) |
|---|---|
| 第2位 | 認知症 |
| 第3位 | 骨折・転倒 |
脳血管障害は、脳の血管が破れたり詰まったりする疾患です。くも膜下出血や脳梗塞が当てはまります。後遺症により、麻痺が残る、寝たきりになるなどのリスクも高く、介護が必要になる大きな要因です。
認知症は、症状が重くなるにつれ介護の必要性が高くなります。初期段階では同じ話を繰り返したり探し物が増えたりする程度ですが、認知症が進行すると、家族の顔が分からなくなったり反応が鈍くなったりします。
排泄物を壁に擦り付けるなど、周辺症状といわれる行動がみられる方も多く、進行すると介護の手間も大きくなります。
骨折や転倒も、介護が必要になる原因のひとつです。高齢者の転倒で危険なのは、大腿骨(股関節周りの太ももの骨)の骨折です。
高齢になると骨折の完治までに時間がかかるため、大腿骨の骨折をきっかけに寝たきりになり、気力が落ちて心身とともに機能が低下してしまう方が少なくありません。
ケアマネジャーが知る要介護5に認定されたケース
ケアマネジャーが3つの例を紹介するっポ。
ここでは、要介護5に認定された要因や状態について、ケアマネジャーが実際に知るケースをもとに3つの例を紹介します。
脳血管障害による意識障害
くも膜下出血のような脳血管障害で要介護5の認定を受けた方は、認知機能の低下や昏睡状態がみられ、意思疎通が困難だったり、寝たきりの状態だったりするケースが少なくありません。
新規の申請で要介護5となる方は多くありませんが、意識障害の程度によっては常に介護が必要と判断され、要介護5となるケースがあります。
進行性疾患による寝たきり状態
パーキンソン病やアルツハイマー型認知症の末期など、進行性疾患によって徐々に体が動かなくなり、寝たきり状態になった方が要介護5の判定を受けるケースもあります。
状態にもよりますが、寝たきりになると食事や排泄はもちろん、体を横に向けるのも自力では難しくなります。そのため、介護の手間によっては要介護5となるケースもあります。
酸素療法などの医療ケアが欠かせない
要介護5の判定が出ている方には、酸素療法や経管栄養、吸引のような医療ケアを必要としている方もたくさんいます。
要介護5は、そもそも生活全般で介護を必要とする状態ですが、医療ケアも必要となると自宅での生活がより難しくなります。病院や施設で生活している方も多いのが要介護5の特徴です。
要介護5の介護期間
介護が続く期間はどのくらいなのかな…。
要介護5は、日常生活のほぼすべてで介護を要する状態です。しかし、同じ要介護度であっても心身の状態や年齢などは人によって異なるため、要介護5の認定を受けてからの介護期間や余命はそれぞれで違います。
参考までに、要介護者全体の介護期間を調査したデータがあります。生命保険文化センターの報告によると、介護期間の平均は4年7カ月でした。
4~10年未満がもっとも多く27.9%、10年以上は14.8%で、42.7%に4年以上の介護期間があることが分かります。
| 6カ月未満 | 6.1% |
|---|---|
| 6カ月~1年未満 | 6.9% |
| 1~2年未満 | 15.0% |
| 2~3年未満 | 16.5% |
| 3~4年未満 | 11.6% |
| 4~10年未満 | 27.9% |
| 10年以上 | 14.8% |
| 不明 | 1.3% |
| 平均 | 4年7カ月 |
要介護認定では、新規で要介護5となるケースは多くありません。そのため、要介護5の状態での介護期間は、平均の4年7カ月よりも短い可能性があります。
ただし、要介護5は要介護度でもっとも重い状態です。家族だけでの介護は大きな負担となるため、介護サービスを利用してできるだけ負担を減らしましょう。
要介護5で利用できる介護保険サービス
要介護5では、すべての介護保険サービスを利用できるっポ。
要介護度によっては利用できない介護保険サービスもありますが、要介護5ではすべてのサービスを利用できます。
| 自宅で受ける | ・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導 |
|---|---|
| 施設に通う | ・デイサービス ・デイケア |
| 施設に宿泊する | ・短期入所生活介護 ・短期入所療養介護 |
| 施設に入居する | ・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・特定施設入居者生活介護 ・介護医療院 |
| 福祉用具やリフォーム | ・福祉用具貸与 ・特定福祉用具販売 ・住宅改修 |
| 地域密着型サービス |
訪問 通所 通い・訪問・泊り 入居施設 |
以下で、それぞれのサービス内容と費用について解説します。
なお、費用は1単位10円・1割負担での計算です。
自宅で受けるサービス
要介護5の方が自宅で受けられる介護保険サービスは以下です。
訪問介護
利用者の自宅を訪問介護員が訪問し、食事や排泄などの身体介護、調理や掃除などの生活援助を行うサービスです。通院時の乗降車や移送などの対応も行います。
| 20分未満 | 163円 |
|---|---|
| 20分以上30分未満 | 244円 |
| 30分以上1時間未満 | 387円 |
| 1時間以上 | 567円(30分増すごとに+82円) |
| 20分以上45分未満 | 179円 |
|---|---|
| 45分以上 | 220円 |
| 片道 | 97円 |
|---|
訪問入浴介護
利用者の自宅を介護職員と看護職員が訪問し、持参した専用の浴槽で入浴介護を行うサービスです。状態によっては部分浴や体拭きなどで対応します。
| 全身浴 | 1,266円 |
|---|---|
| 清拭または部分浴 | 1,139円 |
訪問看護
利用者の自宅を看護師やリハビリテーション専門職員が訪問し、医師の指示に基づいて病状の確認や療養上の世話、診療の補助などを行うサービスです。看取りにも対応します。
| 20分未満 | 314円 |
|---|---|
| 30分未満 | 471円 |
| 30分以上1時間未満 | 823円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1,128円 |
| 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問(20分) | 294円 |
| 20分未満 | 266円 |
|---|---|
| 30分未満 | 399円 |
| 30分以上1時間未満 | 574円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 844円 |
訪問リハビリテーション
利用者の自宅をリハビリテーション専門職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)が訪問し、医師の指示でリハビリ―ションを行うサービスです。
| 20分 | 308円 |
|---|
居宅療養管理指導
通院が困難な利用者の自宅を、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士が訪問し、療養上の助言や指導・管理などを行うサービスです。
| 医師(月2回) | 515円 |
|---|---|
| 歯科医師(月2回) | 517円 |
| 薬局の薬剤師(月4回) | 518円 |
| 管理栄養士(月2回) | 545円 |
| 歯科衛生士(月4回) | 362円 |
施設に通うサービス
要介護5の方が施設に通って受けられるサービスは以下です。
デイサービス
利用者が日帰りで施設に通い、食事や入浴などの日常生活の世話、レクリエーションなどを受けるサービスです。高齢者の外出の機会になり、家族の介護負担を軽減できます。
要介護5では、以下の介護保険費用がかかります。
| 3時間以上4時間未満 | 588円 |
|---|---|
| 4時間以上5時間未満 | 617円 |
| 5時間以上6時間未満 | 984円 |
| 6時間以上7時間未満 | 1,008円 |
| 7時間以上8時間未満 | 1,148円 |
| 8時間以上9時間未満 | 1,168円 |
デイケア
利用者が日帰りで施設に通い、リハビリテーションを受けるサービスです。食事や入浴、日常生活上の支援なども行います。
要介護5では、以下の介護保険費用がかかります。
| 1時間以上2時間未満 | 491円 |
|---|---|
| 2時間以上3時間未満 | 612円 |
| 3時間以上4時間未満 | 842円 |
| 4時間以上5時間未満 | 957円 |
| 5時間以上6時間未満 | 1,120円 |
| 6時間以上7時間未満 | 1,290円 |
| 7時間以上8時間未満 | 1,379円 |
施設に宿泊するサービス
要介護5の方が施設に宿泊して受けられるサービスは以下です。
短期入所生活介護(ショートステイ)
利用者が施設に宿泊し、食事や入浴などの日常生活上の支援、機能訓練などを受けるサービスです。連続で30日間利用できます。
要介護5の人が1日あたりにかかる介護保険の費用は以下です。この他に、滞在費などが自費でかかります。
| 従来型個室・多床室 | 単独型 | 926円 |
|---|---|---|
| 併設型 | 884円 | |
| ユニット型 | 単独型 | 1,028円 |
| 併設型 | 987円 |
短期入所療養介護(ショートステイ)
利用者が施設に宿泊し、療養に必要な世話や日常生活上の支援などを受けるサービスです。介護老人保健施設や介護医療院などがサービスを提供しています。
要介護5の人が1日あたりにかかる介護保険の費用は以下です。この他に、滞在費などが自費でかかります。
| 従来型個室 | 基本型 | 971円 |
|---|---|---|
| 在宅強化型 | 1,074円 | |
| 多床室 | 基本型 | 1,052円 |
| 在宅強化型 | 1,161円 | |
| ユニット型 | 基本型 | 1,056円 |
| 在宅強化型 | 1,165円 |
施設に入居するサービス
要介護5はもっとも重い要介護度のため、施設に入居する方も少なくありません。要介護5の方が入居できる介護保険施設は以下です。
特別養護老人ホーム
原則として要介護3以上の方が入居できる介護保険施設です。日常生活の支援や機能訓練などを受けられます。
要介護5の人が1日あたりにかかる介護保険の費用は以下です。この他に、居住費などが自費でかかります。
| 従来型個室・多床室 | 871円 |
|---|---|
| ユニット型 | 955円 |
介護老人保健施設
在宅復帰を目的とする方が入居する施設です。在宅と施設の中間の役割を担い、日常生活の支援のほかに、リハビリテーションや医療も受けられます。
要介護5の人が1日あたりにかかる介護保険の費用は以下です。この他に、居住費などが自費でかかります。
| 従来型個室 | 基本型 | 932円 |
|---|---|---|
| 在宅強化型 | 1,040円 | |
| 多床室 | 基本型 | 1,012円 |
| 在宅強化型 | 1,125円 | |
| ユニット型 | 基本型 | 1,018円 |
| 在宅強化型 | 1,130円 |
特定施設入居者生活介護
日常生活の支援や機能訓練などを受けられる入居サービスです。指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどが該当します。
要介護5の人が1日あたりにかかる介護保険の費用は以下です。この他に、居住費などが自費でかかります。
| 813円 |
介護医療院
療養を必要とする方が、医療・看護、日常生活の支援などを受けられる入居サービスです。
要介護5の人が1日あたりにかかる介護保険の費用は以下です。この他に、居住費などが自費でかかります。
| 従来型個室 | Ⅰ型(Ⅰ) | 1,263円 |
|---|---|---|
| Ⅱ型(Ⅰ) | 1,149円 | |
| 多床室 | Ⅰ型(Ⅰ) | 1,375円 |
| Ⅱ型(Ⅰ) | 1,261円 | |
| ユニット型 | Ⅰ型(Ⅰ) | 1,392円 |
| Ⅱ型(Ⅰ) | 1,374円 |
福祉用具・リフォームのサービス
要介護5の方が利用できる福祉用具やリフォームに関するサービスは以下です。
福祉用具貸与
利用者の状況や希望をふまえて、適切な福祉用具をレンタルできるサービスです。要介護5ではすべての品目をレンタルできます。
以下は1カ月あたりの金額の目安ですが、商品や事業所によって大きく異なります。
| 車椅子 | 300円くらい |
|---|---|
| 車椅子の付属品 | 200円くらい |
| 特殊寝台(電動ベッド) | 900円くらい |
| 特殊寝台の付属品 | 100円くらい |
| 床ずれ防止用具 | 500円くらい |
| 体位変換器 | 100円くらい |
| 手すり(取り付け工事をしないもの) | 300円くらい |
| スロープ(取り付け工事をしないもの、段差解消のためのもの) | 500円くらい |
| 歩行器 | 300円くらい |
| 歩行補助つえ | 100円くらい |
| 認知症老人徘徊感知機器 | 600円くらい |
| 移動用リフト | 2,000円くらい |
| 自動排泄処理装置 | 800円くらい |
特定福祉用具販売
利用者が少ない負担で福祉用具を購入できるサービスです。
年間10万円が上限となり、10万円を超えた分は全額自己負担となります。費用は利用者がいったん立て替えて、所得に応じて7~9割が現金で払い戻される償還払いが一般的です。
要介護5で購入できる福祉用具は以下です。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部分
- 簡易浴槽
- 入浴補助用具
- 移動用リフトのつり具部分
- 排泄予測支援機器
- 固定用スロープ
- 歩行器 ※歩行車は除く
- 歩行補助つえ ※松葉杖は除く
住宅改修
身体が不自由になっても自宅での生活を続けられるように、住宅をリフォームするサービスです。
介護保険による上限は一人につき20万円で、支払い方法は特定福祉用具販売と同じく償還払いが一般的です。
地域密着型サービス
地域密着型サービスには、地域密着型デイサービスや夜間対応型訪問介護など複数ありますが、ここでは主な2つのサービスを紹介します。
グループホーム
認知症の方を対象とした入居サービスです。施設では日常生活上の支援を受けられます。1ユニット最大9名が入居し、少人数での家庭的な環境のなかで生活を送ります。
要介護5の人が1日あたりにかかる介護保険の費用は以下です。この他に、居住費などが自費でかかります。
| (Ⅰ)※1ユニット | 859円 |
|---|---|
| (Ⅱ)※2ユニット以上 | 845円 |
小規模多機能型居宅介護
通い・訪問・泊まりを組み合わせて利用できるサービスです。住み慣れた地域で可能な限り暮らし続けられるように、3つのサービスを柔軟に組み合わせて利用できます。
要介護5の人が1カ月にかかる介護保険の費用は以下です。
| 同一建物に居住する者以外 | 27,209円 |
|---|---|
| 同一建物に居住する者 | 24,516円 |
要介護5のケアプラン例
要介護5のケアプラン例を2つ紹介するっポ。
要介護5の方が利用する介護保険サービスについて、以下でケアプランの例を紹介します。費用の計算は1単位10円・1割負担です。
夫婦二人暮らしのAさん
寝たきり状態のAさんは、夫と自宅で暮らしています。意思疎通が難しく、すべての行為に対して介護が必要です。
自宅での療養生活の質を向上させるために、訪問看護や居宅療養管理指導を利用しています。また、外出の機会を作ること、夫の介護負担を軽減させることを目的に、デイサービスとショートステイも利用しています。
介護ベッドや車椅子など、必要な福祉用具はレンタルで対応しています。
配食サービスなどの介護保険適用外のサービスも利用しながら、自宅での生活を続けている状態です。
| 介護サービス | 利用回数/月 | 利用時間/回 | 自己負担額/月 |
|---|---|---|---|
| デイサービス | 26回 | 5時間以上6時間未満 | 25,584円 |
| 短期入所療養介護 | 4回(2日) | ― | 3,884円 |
| 訪問看護 | 4回 | 30分未満 | 1,884円 |
| 居宅療養管理指導(医師) | 2回 | ― | 515円 |
| 居宅療養管理指導(薬剤師) | 4回 | ― | 518円 |
| 福祉用具貸与(ベッド) | ― | ― | 1,000円 |
| 福祉用具貸与(サイドレール2本) | ― | ― | 50円 |
| 福祉用具貸与(床ずれ防止用具) | ― | ― | 500円 |
| 福祉用具貸与(体位変換器2つ) | ― | ― | 200円 |
| 福祉用具貸与(車椅子) | ― | ― | 500円 |
| 福祉用具貸与(スロープ) | ― | ― | 500円 |
| 自己負担額の合計 | 35,135円 | ||
息子夫婦と同居するBさん
息子夫婦と同居しているBさん。認知症の周辺症状が顕著で、食べ物以外のものを食べようとする異食行為が見られるなど、目が離せない状態です。下肢筋力の低下により移動はレンタルの車椅子を利用していますが、突然立ち歩いては転倒することを繰り返しています。
これまで、訪問介護やデイサービス、ショートステイなどを利用しながら自宅での生活を続けていましたが、1カ月ほど前に排泄物を壁や家具に塗りつけている姿を見て、家族は自宅での介護に限界を感じました。
家族の介護負担軽減を図るため、多めにショートステイを利用することに決めましたが、今後は施設への入居を検討する方針です。
| 介護サービス | 利用回数/月 | 利用時間/回 | 自己負担額/月 |
|---|---|---|---|
| 短期入所生活介護 | 30回(15日) | ― | 29,610円 |
| 福祉用具貸与(車椅子) | ― | ― | 500円 |
| 自己負担額の合計 | 30,110円 | ||
自己負担額はどのくらい?要介護5の支給限度額
要介護5では自己負担額がどのくらいかかるのかな…。
介護保険サービスは自己負担1~3割の費用で利用できますが、少ない費用負担で利用できる額には上限があります。この上限を区分支給限度額といい、限度額を超えた分は全額が自己負担となります。
| 要支援1 | 5,032円 |
|---|---|
| 要支援2 | 10,531円 |
| 要介護1 | 16,765円 |
| 要介護2 | 19,705円 |
| 要介護3 | 27,048円 |
| 要介護4 | 30,938円 |
| 要介護5 | 36,217円 |
※1割負担、1単位10円で計算
要介護5は要介護度がもっとも重く、支給限度額もいちばん高くなります。要介護5の支給限度額はおよそ36万2,170円で、1割負担であれば約36,217円が限度額です。
この金額は地域により多少前後する可能性があるため、詳しくはケアマネジャーやお住いの市区町村にご確認ください。
要介護5でもらえるお金・給付金はある?
要介護5の方の介護では、利用する介護・医療のサービスの増加により費用負担が大きくなる可能性があります。
以下の制度を活用すると、費用負担を軽減できます。
費用負担を軽減する制度を活用したい方は、役所窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーなどに相談しましょう。
高額介護サービス費
介護サービスの利用が支給限度額を超えたときに、超過分を受けとれる。市町村に申請する必要がある。
高額医療・高額介護合算制度
医療保険と介護保険を合算し、限度額を超えたときに、超過分を受けとれる。医療保険が同じであれば世帯での合算が可能。
特定入所者介護サービス費
対象は低所得の方。特養などの介護保険施設、ショートステイを利用したときの食費や居住費が軽減される。
障害者控除
精神または身体に障害があるなど一定の条件を満たしている方が対象。所得が控除される。
おむつ費用の助成
実施の有無や内容は自治体による異なる。現物給付、助成券の配布など。
要介護5に関するよくある質問
要介護5に関するよくある質問を紹介するっポ。
要介護5は、介護なしで日常を送れない状態です。今後どのように介護していくべきか、迷いや不安を抱えるご家族もいらっしゃると思います。
ここでは、要介護5に関するよくある質問にケアマネジャーである筆者が回答します。
・要介護5で在宅介護は無理?
・要介護5は特養への入居が優先される?入れないことはある?
要介護5から回復する可能性はある?
要介護5から要介護度が軽くなる可能性はゼロではありません。
以前、ほとんど寝たきり状態だった要介護5の方が、要介護2になったケースがありました。
その方は要介護5で退院し、そのまま老健に入居。老健でリハビリテーションに励んだことが功を奏し、その後は自宅復帰を果たしました。
要介護5からの回復は簡単ではありませんが、要介護状態になっても能力の維持・向上はできます。
そのためには、本人の意欲だけでなく周りのサポートも重要です。介護サービスの内容をケアマネジャーと相談したり、家族ができる支援を専門家に聞いたりすることで、要介護5からの回復を目指せます。
要介護5で在宅介護は無理?
要介護5でも在宅介護は可能です。生命保険文化センターの調査によると、要介護5の方が在宅介護を受けている割合は44.1%でした。
| 在宅 | 44.1% |
|---|---|
| 施設 | 54.9% |
| その他 | 1.0% |
施設で介護を受ける方が半数を超えていますが、在宅との差はわずかです。介護サービスの適切な利用や家族の援助により、要介護5の方も住み慣れた自宅での生活を送れます。
要介護5は特養への入居が優先される?入れないことはある?
要介護5の方は、特別養護老人ホームへの入居が優先される可能性があります。なぜなら、特養に入居する順番は申し込み順ではなく、優先順位によって決まるからです。
特養は費用が比較的安く、人気のある施設です。空きがなく入居待ちが発生している特養も少なくありません。
優先順位は、介護を必要とする程度や家族の状況などを鑑みて決定されます。要介護5は介護なしでの日常生活がほぼ不可能な状態のため、優先順位が高くなる可能性があります。
それでも早く入れないときは、複数の特別養護老人ホームに申し込むなどすると早く入居しやすくなるでしょう。
要介護5のまとめ
要介護5は、介護がなければ日常生活を送れない状態です。寝たきりや認知症により意思疎通が困難な方も多く、介護にかかる手間は少なくありません。
家族には大きな介護負担がかかることが考えられるため、介護サービスを上手に利用して負担を減らすとよいでしょう。
要介護5では、施設で生活を送る方も大勢います。場合によっては施設への入居も検討し、ケアマネジャーや周りの助けを借りながら、ご本人やご家族が安心した生活を送れるようにしてください。
こちらもおすすめ
おすすめ事業所情報
新着記事
ハートページ誌は、全国約70市区・約100万部を発行する業界最大級の介護情報誌。20年を超える歴史(2001年創刊)、カバーするエリアの広さ、発行部数、各自治体や連絡協議会と連携し制作された信頼性の高さで、介護に関わるみなさまより高い評価を得ています。
ハートページナビでは、介護情報を専門に扱うサイトとして、介護に関わる皆さまに必要な情報、役立つ情報などを掲載しています。