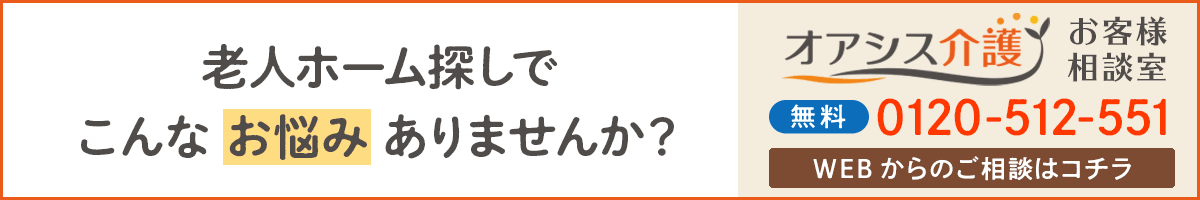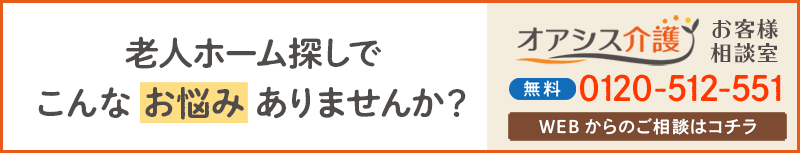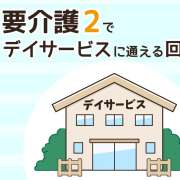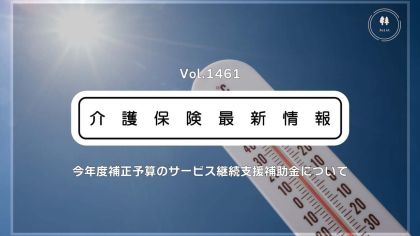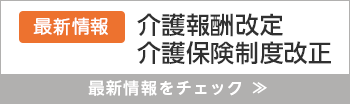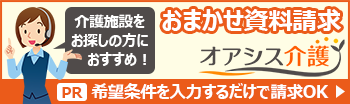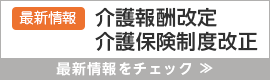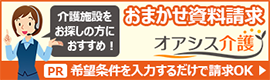要介護2は、要支援1から要介護5まである介護度のちょうど中間に位置しています。
要介護2の状態や、要介護1・3との違い、受けられる介護保険サービスの内容と費用目安、ケアプラン例などを紹介します。
今後の見通しを立てるためにも、ぜひ参考にしてくださいね。
・要介護2とはどんな状態?
・要介護2と要介護1の違い
・要介護2と要介護3の違い
・要介護2に当てはまる認知症の症状はある?
・要介護2に認定されると暮らしは変わる?
・要介護2で受けられる介護保険サービスの種類と費用
・要介護2は特別養護老人ホームに入居できない?
・要介護2で活用できる介護保険適用外のサービス
・要介護2のケアプラン事例
・要介護2の支給限度額
・要介護2に関するよくある質問
・要介護2のまとめ
要介護2とはどんな状態?
要介護2はどんな状態なのかな。
要介護2は、生活のさまざまな場面で何らかの支援を必要とする状態です。次のような状態に当てはまると、要介護2に判定される可能性が高くなります。
- 身だしなみや部屋の掃除などの身の回り全般に、見守りや声掛けを要する
- 立ち上がりや段差を上がるときなどに、手すりや支えを要する
- 移動の際に杖や歩行器、もしくは手引きなどを要する
- 排泄や食事の動作に介助を要する
- 加齢や認知症状などにより、理解力の低下や混乱が見られる
要介護認定の基準に当てはめると、要介護2は要介護認定等基準時間が50分以上70分未満、またはこれに相当する状態を指します。
要介護認定等基準時間は、日常的な介助や医療関連など、以下の行為に要する時間を計算して数値化したものです。
この時間はあくまで「介護の手間」をはかる「ものさし」のため、介護にかかる実際の時間とは異なります。
| 行為の区分 | 具体的な内容 | |
|---|---|---|
|
直接生活介助 |
食事 | 食事にまつわる行為 |
| 排泄 | トイレ・排泄にまつわる行為 | |
| 移動 | 移動にまつわる行為 | |
| 清潔保持 | 入浴、衣類の着脱等 | |
| 間接生活介助 | 洗濯、掃除等の家事援助等 | |
| BPSD 関連行為 | 徘徊に関する探索、不潔な行為に関する後始末等 | |
| 機能訓練関連行為 | 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練 | |
| 医療関連行為 | 輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助 | |
要介護度別の要介護認定等基準時間は以下になります。
| 要介護認定等基準時間 | |
|---|---|
| 非該当 | 25 分未満 |
| 要支援1 | 25分以上32分未満 またはこれに相当する状態 |
| 要支援2 | 32分以上50分未満 またはこれに相当する状態 |
| 要介護1 | |
| 要介護2 | 50分以上70分未満 またはこれに相当する状態 |
| 要介護3 | 70分以上90分未満 またはこれに相当する状態 |
| 要介護4 | 90分以上110分未満 またはこれに相当する状態 |
| 要介護5 | 110分以上 またはこれに相当する状態 |
要介護2の介護期間は?
要介護度別の寿命や平均余命についての調査はありませんが、生命保険文化センターの調査(2024年)によると、介護期間の平均は約4年7カ月でした。
| 6カ月未満 | 6.1% |
|---|---|
| 6カ月~1年未満 | 6.9% |
| 1~2年未満 | 15.0% |
| 2~3年未満 | 16.5% |
| 3~4年未満 | 11.6% |
| 4~10年未満 | 27.9% |
| 10年以上 | 14.8% |
| 不明 | 1.3% |
| 平均 | 4年7カ月 |
これは要介護度を限定しない調査結果で、現在進行形の介護も含みます。
介護の終わりはわからず、10年以上続く人も16.1%います。介護期間の予測は難しいといえるでしょう。
要介護2と要介護1の違い
要介護2は要介護1から一段階が上がった状態で、より手助けが必要になるっポ。
要介護1は、部分的な介護を必要とする状態です。排泄や食事、入浴などの動作は問題なくても、洗濯や掃除、調理などには介護を要します。
要介護2は、要介護1の状態に加えて、排泄や食事、入浴などにも部分的な介護が必要な状態です。買い物や食事の準備、トイレまで移動して排泄する行為などにも、一部で介護が必要になります。
要介護2と要介護3の違い
要介護3は要介護2より状態が重いっポ。
要介護3は、要介護2よりも状態が悪化します。排泄や食事、掃除、洗濯などの能力がさらに低下し、全面的な介護が必要です。
たとえば排泄の際に、要介護2ではズボンの上げ下げを介助するのみだったのが、要介護3では拭き取りや水洗など一連の動作に介護を要します。
要介護2に当てはまる認知症の症状はある?
要介護2には認知症の方もいますが、症状によって要介護度を判断することはできません。
要介護度はさまざまな視点をもとに判断され、そのなかのひとつに「認知症の日常生活自立度」を図る基準があります。
「認知症の日常生活自立度」は、以下のⅠ~Mのランクで判断されます。
ランクⅠ
何らかの認知症状がありますが、日常生活はほぼ自立しています。もの忘れやものごとの段取りなどが分からなくなっても、少しの指示や助言があれば日常生活を送れる状態です。
ランクⅡ
日常生活に支障が出る症状や行動が多少あっても、誰かが注意していれば自立できる状態です。ランクⅡはさらに2つに分けられます。
Ⅱa
家庭外でランクⅡの状態がみられ、たびたび道に迷う、これまでできていた買い物や金銭管理などにミスが目立ちます。
Ⅱb
家庭内でもランクⅡの状態がみられ、服薬管理や電話・訪問者の対応などができず、ひとりでの留守番が困難です。
ランクⅢ
日常生活に支障が出る症状・行動や、意思疎通の難しさがあり介護が必要です。
着替え、食事、排泄がうまくできず、時間がかかることがあります。また、徘徊や火の不始末、不潔行為なども見られます。
Ⅲa
主に日中にランクⅢの状態がみられます。
Ⅲb
主に夜間にランクⅢの状態がみられます。
ランクⅣ
日常生活に支障が出る症状・行動や、意思疎通の難しさが頻繁にあり常に介護が必要です。見られる症状・行動はランクⅢと同様です。
ランクM
著しい精神症状や問題行動、重篤な身体疾患があり、専門医療が必要です。自傷、他害、せん妄想や、精神状態に起因する問題行動が続きます。
要介護2に認定されると暮らしは変わる?
要介護2の人は一人暮らしできるのかな。
要介護2では、洗濯や掃除に対する支援のほかに、排泄や入浴などにも一部で介護が必要になります。要介護2に認定されると暮らしに変化は出るのでしょうか。
以下のふたつについて解説します。
・要介護2で運転や免許更新はできる?
要介護2で一人暮らしはできる?
介護サービスを利用したり、家族ができない部分を支援したりすれば、要介護2でも一人暮らしを続けられます。
要介護2は、日常生活の動作に部分的な介護が必要な状態です。たとえば、入浴時に浴槽をまたいだり背中を洗ったりすることが難しい方なら、できない部分は訪問介護のサポートを受けることで自宅での入浴を続けられます。
また、寝床からの起き上がりや歩行が困難な方は、介護保険で介護ベッドを借りたり自宅に手すりをつけたりすれば、安全に生活しやすくなります。
要介護2で運転や免許更新はできる?
要介護2でも自動車の運転や免許証の更新はできますが、運転できる状態かどうかは人それぞれです。
ただし、75歳以上の方は運転免許を更新する際に、認知機能検査などを受ける必要があります。検査により認知症のおそれがあると判定された方は、別の検査や医師の診断を受けなければなりません。最終的に認知症と診断されると、免許の取り消し・停止となります。
また、一定の違反歴のある方は運転技能検査を実施します。合格しなければ免許証は更新できません。
高齢になると安全な運転ができなくなる可能性があります。免許証の返納も検討し、高齢者の安全を守るとよいでしょう。
要介護2で受けられる介護保険サービスの種類と費用
要介護2で利用できる介護保険サービスは?
要介護2の方は、ほとんどの介護保険サービスを受けられます。
以下は、要介護2で利用できる介護保険サービスの一覧です。
| 自宅で受ける | ・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導 |
|---|---|
| 施設に通う | ・デイサービス ・デイケア |
| 施設に宿泊する | ・短期入所生活介護 ・短期入所療養介護 |
| 施設に入居する | ・介護老人保健施設 ・特定施設入居者生活介護 ・介護医療院 |
| 福祉用具やリフォーム | ・福祉用具貸与 ・特定福祉用具販売 ・住宅改修 |
| 地域密着型サービス |
訪問 通所 通い・訪問・泊り 入居施設 |
以下で各サービスの内容と費用の目安を紹介します。
費用は、1割負担、1単位10円で計算しています。
自宅で受けるサービス
ヘルパーや看護師などが、利用者の自宅を訪問する介護保険サービスです。要介護2ではすべての訪問サービスを利用できます。
訪問介護
ヘルパーが利用者の自宅を訪問し、掃除・洗濯などの生活支援、入浴・排泄・起き上がりなどの身体介助を行う介護保険サービスです。通院などを目的とした車の乗り降りや移送のサービスも行います。
| 20分未満 | 163円 |
|---|---|
| 20分以上30分未満 | 244円 |
| 30分以上1時間未満 | 387円 |
| 1時間以上 | 567円(30分増すごとに+82円) |
| 20分以上45分未満 | 179円 |
|---|---|
| 45分以上 | 220円 |
| 片道 | 97円 |
|---|
訪問入浴介護
看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、入浴介護を行う介護保険サービスです。簡易浴槽を持ち込み、自宅での入浴が困難な方の清潔保持や心身機能の維持を図ります。
| 全身浴 | 1,266円 |
|---|---|
| 清拭または部分浴 | 1,139円 |
訪問看護
看護師などが利用者の自宅を訪問し、療養上の世話や健康チェック、薬の管理などを行う介護保険サービスです。医師の指示に基づいた支援が行われます。
| 20分未満 | 314円 |
|---|---|
| 30分未満 | 471円 |
| 30分以上1時間未満 | 823円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1,128円 |
| 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問(20分) | 294円 |
| 20分未満 | 266円 |
|---|---|
| 30分未満 | 399円 |
| 30分以上1時間未満 | 574円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 844円 |
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が利用者の自宅を訪問し、リハビリを行う介護保険サービスです。医師の指示に基づいてサービスを提供します。
| 20分 | 308円 |
|---|
居宅療養管理指導
医師や薬剤師などが利用者の自宅を訪問し、療養上の管理や指導をする介護保険サービスです。利用できるのは通院が難しい方となります。
| 医師(月2回) | 515円 |
|---|---|
| 歯科医師(月2回) | 517円 |
| 薬局の薬剤師(月4回) | 518円 |
| 管理栄養士(月2回) | 545円 |
| 歯科衛生士(月4回) | 362円 |
施設に通うサービス
要介護2の方が施設に通って受けられるサービスは次の2つです。
デイサービス
日帰りで施設に通い、食事や入浴、レクリエーションなどのサービスを受けられる介護保険サービスです。高齢者が外出するきっかけになり、家族の介護負担も減らせます。送迎もあるため行き帰りも安心です。
| 3時間以上4時間未満 | 423円 |
|---|---|
| 4時間以上5時間未満 | 444円 |
| 5時間以上6時間未満 | 673円 |
| 6時間以上7時間未満 | 689円 |
| 7時間以上8時間未満 | 777円 |
| 8時間以上9時間未満 | 791円 |
デイケア
病院や介護老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士などからリハビリを受けられる介護保険サービスです。リハビリは医師の指示に基づいて提供されます。
| 1時間以上2時間未満 | 398円 |
|---|---|
| 2時間以上3時間未満 | 439円 |
| 3時間以上4時間未満 | 565円 |
| 4時間以上5時間未満 | 642円 |
| 5時間以上6時間未満 | 738円 |
| 6時間以上7時間未満 | 850円 |
| 7時間以上8時間未満 | 903円 |
施設に宿泊するサービス
要介護2の方が宿泊できる介護保険サービスは2種類で、どちらもショートステイです。
短期入所生活介護(ショートステイ)
短期間施設に宿泊し、日常生活の支援などを受ける介護保険サービスです。家族が出張などで介護できないときや、家族の介護負担の軽減などを目的に利用します。連続利用は30日までです。
以下の1日あたりにかかる介護保険の費用の他に、滞在費などが自費でかかります。
| 従来型個室・多床室 | 単独型 | 715円 |
|---|---|---|
| 併設型 | 672円 | |
| ユニット型 | 単独型 | 815円 |
| 併設型 | 772円 |
短期入所療養介護(ショートステイ)
短期間施設に宿泊し、医療や機能訓練、日常生活上の世話を受ける介護保険サービスです。介護老人保健施設や介護医療院などに宿泊します。連続利用は30日までです。
以下の1日あたりにかかる介護保険の費用の他に、滞在費などが自費でかかります。
| 従来型個室 | 基本型 | 801円 |
|---|---|---|
| 在宅強化型 | 893円 | |
| 多床室 | 基本型 | 880円 |
| 在宅強化型 | 979円 | |
| ユニット型 | 基本型 | 883円 |
| 在宅強化型 | 983円 |
施設に入居するサービス
要介護2の方が介護保険を利用して入居できる施設は以下です。
特別養護老人ホームへの入居は原則要介護3以上のためここでは除外していますが、要介護2の方でもやむを得ない事情があれば特例で入居できるケースがあります。
介護老人保健施設
自宅と病院の中間施設で、医療やリハビリを受けて自宅復帰を目指します。略して老健とも呼ばれます。
以下は1日あたりにかかる施設サービス費で、この他に食費や居住費などが別途必要です。
| 従来型個室 | 基本型 | 763円 |
|---|---|---|
| 在宅強化型 | 863円 | |
| 多床室 | 基本型 | 843円 |
| 在宅強化型 | 947円 | |
| ユニット型 | 基本型 | 848円 |
| 在宅強化型 | 952円 |
特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護は、特定施設の指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどで、入居者の日常生活に必要なサービスを行うことです。職員の人員配置や設備基準が細かく決められています。
以下は1日あたりにかかる施設サービス費で、この他に食費や居住費などが別途必要です。
| 609円 |
介護医療院
医療的ケアが常時必要な方に向けた、医療と介護を一体的に提供する長期療養施設です。心身の状態にもよりますが、要介護2では入居まで時間がかかる可能性があります。
以下は1日あたりにかかる施設サービス費で、この他に食費や居住費などが別途必要です。
| 従来型個室 | Ⅰ型(Ⅰ) | 832円 |
|---|---|---|
| Ⅱ型(Ⅰ) | 771円 | |
| 多床室 | Ⅰ型(Ⅰ) | 943円 |
| Ⅱ型(Ⅰ) | 883円 | |
| ユニット型 | Ⅰ型(Ⅰ) | 960円 |
| Ⅱ型(Ⅰ) | 948円 |
福祉用具・リフォームのサービス
要介護2の方が利用できる福祉用具や自宅リフォームの介護保険サービスは以下です。
福祉用具貸与
福祉用具貸与は、車椅子や介護ベッドなどをレンタルできるサービスです。
要介護2は、ほぼすべての品目でレンタルが可能です。自動排泄処理装置は原則として利用できませんが、例外として認められるケースもあります。
- 車椅子
- 車椅子の付属品
- 特殊寝台(電動ベッド)
- 特殊寝台の付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり(取り付け工事をしないもの)
- スロープ(取り付け工事をしないもの、段差解消のためのもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
- 自動排泄処理装置(排便機能を有しない)
以下は、1カ月のレンタル費用の参考例として、特定の商品の料金を掲載しています。
レンタルの費用は事業所や商品によって異なります。また、上限額は定められています。
| 特殊寝台 | 916円 |
|---|---|
| 工事を伴わない手すり | 298円 |
| 歩行補助つえ | 128円 |
特定福祉用具販売
特定福祉用具販売は、介護保険を利用して簡易浴槽や腰掛便座などを購入できるサービスです。上限額は同年度内で10万円となります。
購入できる福祉用具は以下9つで、要介護2ではすべての種目を購入できます。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部分
- 簡易浴槽
- 入浴補助用具
- 移動用リフトのつり具部分
- 排泄予測支援機器
- 歩行器 ※歩行車は除く
- 歩行補助つえ ※松葉杖は除く
住宅改修
住宅改修は、安全に生活できるように自宅をリフォームするサービスです。段差を解消するためのスロープの設置や、和式から洋式便座への取り換えなどができます。
住宅改修はひとつの住宅につき20万円までですが、転居または要介護度が3段階以上重くなると、再度20万円が設定されます。
地域密着型サービス
地域密着型サービには多くの種類がありますが、ここでは要介護2で利用できる主な2つを紹介します。
地域密着型サービはこのほかに、夜間対応型訪問介護や地域密着型デイサービスなどがあります。
グループホーム
認知症の方がアットホームな環境のなかで暮らせる施設です。1ユニット最大9名で共同生活を送るため、他の入居者と馴染みの関係を築けます。
ケアマネジャーが配置され、グループホーム内で介護保険サービスが完結する仕組みです。
以下は1日あたりにかかる施設サービス費で、この他に食費や居住費などが別途必要です。
| (Ⅰ)※1ユニット | 801円 |
|---|---|
| (Ⅱ)※2ユニット以上 | 788円 |
小規模多機能型居宅介護
ひとつの事業所が通い・訪問・宿泊を提供する介護保険サービスです。通い・訪問・宿泊のサービスを組み合わせ、一人ひとりのニーズに合わせたサービスを提供します。
要介護2の方が1カ月にかかる介護保険の費用は以下です。
| 同一建物に居住する者以外 | 15,370円 |
|---|---|
| 同一建物に居住する者 | 13,849円 |
要介護2は特別養護老人ホームに入居できない?
特養への入居は要介護3から?
要介護2では入居できないのかな…。
要介護2は生活全般に支援が必要な状態です。自宅での介護を困難に感じ、特別養護老人ホームへの入居を希望するご家族もいるでしょう。
特養の入居条件は原則として要介護3以上ですが、以下のいずれかに該当する方は、要介護2でも特例として入居が認められる可能性があります。
- 認知症や知的障害、精神障害などにより日常生活に支障をきたす症状や行動が多く、意思疎通が困難な状況が頻繁にみられる
- 家族等による虐待が疑われ、心身の安全や安心の確保が難しい
- 単身もしくは同居家族が高齢や病弱等で家族の支援が期待できない、かつ地域サービスや生活支援サービスが不十分
- 上記以外の理由により、在宅での生活が著しく難しい
なお、特別養護老人ホームは、地域の状況や施設の規模によって入居のしやすさが異なり、入居を希望しても数カ月以上の順番待ちが必要になる可能性があります。
できるだけ早く入居するためには、複数の施設に申し込んでおくなどの工夫が必要です。
要介護2で活用できる介護保険適用外のサービス
介護保険外のサービスも利用すると介護負担をより軽減できるっポ。
介護保険は、要介護者の自立を支援する目的でサービスが提供されるため、望むサービスを受けられない可能性があります。
そのようなときは、介護保険外サービスを利用すると便利です。要介護2を含むすべての要介護度で利用できます。
介護保険外サービスにはたくさんの種類がありますが、例えば以下のようなサービスがあります。
・配食サービス
・介護タクシー
・訪問理美容
・見守りサービス
家事支援・代行サービス
家事を支援・代行するサービスです。訪問介護では、介護保険でできることが決まっています。たとえば、草むしりや大掃除、ペットの世話、季節行事の準備などは、介護保険の範囲外です。これらをお願いしたいときには、家事支援などの保険外サービスを利用すると便利です。
サービス内容は事業所によって異なるため、事前に確かめる必要があります。
配食サービス
高齢者にお弁当を届けるサービスです。栄養バランスのよさはもちろん、その方の状態に合わせて塩分調整食や糖尿病食などを用意している事業所もあります。お弁当を直接受け取ることで、高齢者の安否確認にもなります。
介護タクシー
介護が必要な方を移送するサービスです。車椅子やストレッチャーで乗れる車両があり、ドライバーは介護職員初任者研修を受講しているため、安心して利用できます。
訪問理美容
理美容師が自宅やデイサービスなどを訪問し、サービスを提供します。カットだけでなく、カラーやパーマなどのメニューがそろう事業所もあります。
見守りサービス
高齢者の自宅での生活を見守るサービスです。設置したカメラでの見守りや、緊急通報システム、就寝時の寝返りで安否確認できるものなど、サービスにはさまざまな種類があります。
認知症の方が携帯するGPSなどの購入費を補助する自治体もあります。
要介護2のケアプラン事例
ケアマネジャーが要介護2のケアプラン例を紹介するっポ!
要介護2の方は介護サービスをどのように組み合わせて利用しているのか、事例をもとにしたケアプランを紹介します。
記載は介護保険サービスのみで、1割負担・1単位10円で計算しています。
脳梗塞後遺症で右麻痺のあるAさん
85歳のAさんは妻と二人暮らし。80歳のときに脳梗塞で入院し、右半身に麻痺があります。退院後は歩行が不安定でたびたび転倒していたため、移動時にはレンタルの歩行器を使用しています。
自宅では83歳の妻がAさんの介護をしていますが、高齢の妻にかかる負担は少なくありません。そのため、1日6時間のデイケアを週3回利用して妻が休める時間を設けています。
最近はAさんの物忘れの頻度が増えたことから、施設入居を視野に入れて月3日はショートステイも利用しています。
| 介護サービス | 利用回数/月 | 利用時間/回 | 自己負担額/月 |
|---|---|---|---|
| デイケア | 12回 | 6時間 | 10,200円 |
| 短期入所生活介護 | 6回(3日) | ― | 4,290円 |
| 福祉用具貸与(歩行器) | ― | ― | 330円 |
| 自己負担額の合計 | 14,820円 | ||
認知症の進行が心配な一人暮らしのBさん
83歳のBさんは一人暮らし。認知症の症状があります。唯一の家族である長男は県外に住んでいるため、何かあってもすぐに駆け付けられません。
Bさんはもともと内向的な性格で、慣れていない場所に出かけるのが苦手なタイプ。そのため、通い・訪問・泊りのサービスを一体的に受けられる小規模多機能型居宅介護で、通いを週3回、訪問を週2回、宿泊を週1回利用しています。
以前は徘徊で警察に何度も保護されていましたが、生活リズムや環境が整い、徘徊が見られなくなりました。
| 介護サービス | 利用回数 | 利用時間 | 自己負担額/月 |
|---|---|---|---|
| 小規模多機能型居宅介護 | 毎日 | ― | 15,370円 |
| 自己負担額の合計 | 15,370円 | ||
要介護2の支給限度額
要介護度ごとに支給限度額が決まっているっポ。
介護保険サービスを利用できる金額は、要介護度別に支給限度額が設定されています。介護保険サービスは1~3割の自己負担で利用できますが、限度額を超えた分は全額を自己負担しなければなりません。
要介護2の支給限度額はおよそ197,050円で、1割負担の方だと約19,705円です。
| 要支援1 | 5,032円 |
|---|---|
| 要支援2 | 10,531円 |
| 要介護1 | 16,765円 |
| 要介護2 | 19,705円 |
| 要介護3 | 27,048円 |
| 要介護4 | 30,938円 |
| 要介護5 | 36,217円 |
※1単位10円で計算
地域により多少金額が異なることがあるため、詳しくはケアマネジャーや市区町村にご確認ください。
要介護2に関するよくある質問
要介護2でもらえるお金はある?
おむつの支給はある?
要介護2にまつわるお金の疑問など、よくある質問とその回答を紹介します。
・要介護2でおむつの支給はある?
・要介護2でもらえるお金はある?
・要介護2に認定されるには?
要介護2で障害者手帳はもらえる?
障害者手帳には交付条件があるため、要介護認定を受けているからといって必ず支給されるものではありません。
障害者手帳は「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類で、日常生活に支障をきたしている方に交付されます。
「身体障害者手帳」は視覚・聴覚の障害や肢体に不自由などがある方、「精神障害者保健福祉手帳」は精神障害や高次脳機能障害などがある方、「療育手帳」は知的障害のある方が対象です。
要介護2でおむつの支給はある?
要介護2に認定されても、介護保険制度によるおむつの支給はありません。ただし、自治体によってはおむつの現物支給やおむつ代を助成しています。
実施の有無や詳しい内容は、お住いの地域のホームページや役所窓口などでご確認ください。
要介護2でもらえるお金はある?
要介護2に認定されてももらえるお金はありません。ただし、要介護認定を受けると所得に応じて1~3割の負担で介護保険サービスを利用できます。
1割負担なら、1,000円のサービスを100円で受けられます。直接もらえるお金はありませんが、要介護認定により少ない負担で介護サービスを利用できます。
支給限度額について詳しくはこちら
要介護2に認定されるには?
要介護認定は「要介護2になりたい」と目指したり、狙ったりできるものではありません。要介護度は、介護の手間やその方の状況を総合的に判断して決まるからです。
要介護認定を受けるには、市区町村の窓口に申請する必要があります。要介護認定は以下の流れで進みます。
- 市区町村の窓口で相談する
- 必要な書類を提出する
- 要介護認定調査が行われる
- 一次判定・二次判定が実施される
- 要介護認定の判定結果が届く
申請から原則30日以内に結果が通知されますが、遅れるときは延期通知書が届きます。
要介護度は狙えるものではありませんが、もし結果に納得がいかなければ不服申し立てが可能です。申し立てできる期間は結果を知った翌日から3カ月以内となります。
要介護2のまとめ
要介護2は、生活全般に見守りや一部介助などを必要とする状態です。要介護1よりもできない行為が増え、理解力の低下がみられることもあります。
しかし、適切に介護保険サービスを利用すれば、自立した生活が期待できます。必要に応じて保険外のサービスも組み合わせると、ご家族の介護負担をより軽減できます。
サービスの利用はケアマネジャーともよく相談し、ご本人らしさを大切にした生活を送れるように、またご家族の介護負担を減らせるような介護を目指しましょう。
こちらもおすすめ
おすすめ事業所情報
新着記事
ハートページ誌は、全国約70市区・約100万部を発行する業界最大級の介護情報誌。20年を超える歴史(2001年創刊)、カバーするエリアの広さ、発行部数、各自治体や連絡協議会と連携し制作された信頼性の高さで、介護に関わるみなさまより高い評価を得ています。
ハートページナビでは、介護情報を専門に扱うサイトとして、介護に関わる皆さまに必要な情報、役立つ情報などを掲載しています。